AI要約 (gpt-4.1-nano) この記事のポイント
チック/汚言 自己記録+PDFレポートツール
CBIT(チックに対する包括的行動介入)の考え方を取り入れた自己観察ノート
自己記録レポートツール CBITの考え方にもとづく自己観察サポート
このツールについて
医療機関での相談をスムーズにするための「自己観察ノート」と「PDFレポート」を作るツールです。
- チック/汚言がどんな場面で起こりやすいかを整理します。
- 前触れのムズムズ感に気づく練習のヒントを書き出します。
- 自分で試した「競合する動き」(別の行動)と、その結果をメモします。
- 入力内容から医師に渡せるPDFレポートを作成します。
科学的根拠にもとづき設計されていますが、必ず医師・専門家の治療の補助としてご利用ください。
基本情報(任意)
医師にレポートを渡すときに分かりやすくするための情報です。
いちばん困っているチック/汚言
今、とくに困っている症状を具体的に書いておきます。
悪化しやすい場面・楽になりやすい場面
CBITでは「どんな状況で強くなるか/弱くなるか」を整理することが、とても大切と言われています。
前触れのムズムズ感(プレモニトリー感覚)
「出る前に、なんとなく分かる感覚」があるかどうかを書いておきます。
「競合する動き」のアイデアと試した結果
CBITでは、チックが出そうなときに「代わりに行う動き(競合反応)」を使う練習をします。このツールでは自分で試した工夫をメモすることに特化しています。
・自分や他人の身体を傷つけるような行動(たたく・つねる など)を競合反応にするのはやめましょう。
・具体的なやり方は必ず医師や専門家と相談のうえで決めることをおすすめします。
医師・専門家に伝えたいこと(まとめ)
診察のときにとくに伝えたいことを、自由にまとめてください。
※ 保存はこの端末のブラウザ内(localStorage)のみで行われます。
サーバーには個人の入力内容は送信されません。
このページについて
このページでは、
「チック/汚言 自己記録+PDFレポートツール(CBITベースの自己観察ノート)」 の使い方と、
設計の意図・注意事項・データの扱いについて説明します。
ツール本体は、この記事の少し上にある入力フォームです。
そこに入力した内容は PDFレポートとしてダウンロード でき、
医師や専門家への相談に役立てていただくことを目的にしています。
このツールでできること
このツールは、チックや汚言などの症状でお困りの ご本人やご家族の「自己記録・自己観察」をサポートするツール です。
主に、次のような内容を整理できます。
- いま一番困っているチック/汚言の内容
- どのような場面・状況で強く出やすいか、逆に弱まりやすいか
- 出る前に感じる「ムズムズ感」「違和感」(プレモニトリー感覚)の有無と特徴
- 出そうになったときに試してみた「別の動き・行動(競合する動き)」と、その結果
- 医師・専門家に特に相談したいこと、生活や学校・仕事で困っていること
入力が終わったら、ボタンひとつで PDFレポート を作ることができます。
- PDFは、スマホやPCに保存しておけます
- 印刷して診察時に渡すこともできます
- オンライン診療やメール相談などで、PDFファイルとして医療機関に送ることもできます(医療機関のルールに従ってご利用ください)
なぜ「チック/汚言の自己記録」が大事なのか
1. CBITの考え方をふまえた「整理の枠組み」になっている
チックや汚言に対しては、
CBIT(Comprehensive Behavioral Intervention for Tics:チックに対する包括的行動介入) と呼ばれる行動療法が、
海外を中心に効果が報告されています。
CBITでは、とくに次のような点が重視されます。
- どんな場面・状況・感情のときにチック/汚言が強くなるか
- 出る前に分かる「前触れの感覚」(プレモニトリー感覚)があるか
- その感覚に気づいたとき、代わりに行う安全な「競合する動き」を使えるか
このツールの質問項目は、
CBITで重要とされる視点を、自己記録しやすい形に整理したもの になっています。
そのため、ツールに沿って書いていくだけで、
「どんなときに出やすいのか」
「出る前のサインはあるのか」
「どんな対策を試してみたのか」
といった情報が自然とまとまり、
医師・専門家がCBIT的なアプローチを考えやすい材料 になります。
※このツールはCBITそのものを実施するものではありません。
診断や治療、CBITの指導自体は必ず専門家のもとで行ってください。
2. 「場面・感覚・行動」をセットで見える化できる
ただ「チックが多い/少ない」と数字だけを数えても、
具体的な対策や工夫にはつながりにくいことがあります。
そこでこのツールでは、
- どんな場面で強くなるのか(例:静かな教室、人に見られていると意識したとき など)
- 出る前にどんな感覚があるのか(例:首のムズムズ、胸のモヤモヤ、言葉が頭の中でぐるぐる回る など)
- そのときに試してみた「別の動き・行動」は何か、うまくいったか
を、セットで書き出せるように なっています。
これにより、たとえば
- 「夜の寝る前+疲れている+胸のムズムズが強いときに出やすい」
- 「人前の発表の前は、あらかじめ深呼吸をしておくと少し楽になる」
といった 自分なりのパターン が見つかりやすくなります。
3. 診察の時間を「振り返り」から「相談・検討」に使える
はじめて受診するときや、久しぶりに診察を受けるとき、
「最近はどんな感じでしたか?」
と聞かれても、その場ですべてを思い出して説明するのはとても大変です。
事前にこのツールで整理しておけば、
- 「この期間はこういう場面で特に困っていました」
- 「こんな工夫をしてみて、ここまでは良かったです」
などを、紙1〜2枚のレポートにまとめて伝えることができます。
その結果、診察の時間をより多く
- 治療方針の相談
- 学校や職場への説明の仕方
- ご家族や周囲のサポートの仕方
といった話し合いに使えるようになることが期待できます。
医療行為ではないことについて(重要な注意事項)
このツールは、【あなたのサイト名/提供者名】が
ご本人・ご家族と医療者が「同じ情報を共有しやすくする」ために作成した
自己記録・自己観察用の補助ツール
です。
ですので、次の点をご理解ください。
- このツールは 診断を行うものではありません。
- このツールは 治療方針を決定するものではありません。
- このツールは 薬物療法やCBITなどの専門的な治療の代わりにはなりません。
症状についての最終的な判断や治療方針は、
必ず担当の医師・専門家と相談の上で決めてください。
また、このツールは科学的知見を参考にして設計していますが、
- すべての方に同じ効果を保証するものではないこと
- 利用によって直接的な改善が必ず得られるわけではないこと
も、あらかじめご理解ください。
使い方の流れ
1. ツールのページを開く
- スマホ・タブレット・PCから、このページにアクセスします。
- 入力画面(ショートコード部分)は、この記事の上部に表示されています。
2. 質問項目を、できる範囲で埋めてみる
- いきなり全部を完璧に埋める必要はありません。
- 書きやすいところ・思いつくところから、少しずつ記入してください。
- 後から何度でも書き直し・追記できます。
3. 「この端末に保存」ボタンでブラウザに保存する
- 入力内容は、お使いの端末のブラウザ内(localStorage)に保存されます。
- 当サイトのサーバーには、入力内容は送信されません。
4. PDFレポートをダウンロードする
- 「PDFレポートをダウンロード」ボタンを押すと、
入力内容をもとにしたレポートが自動で作成されます。 - ファイル名には、お名前(ニックネーム)と日付が自動で入ります。
- ダウンロードしたPDFは、
- iPhone/スマホなら「ファイル」やクラウド(iCloud・Google Drive など)に保存
- パソコンならデスクトップやドキュメントに保存
しておくと便利です。
5. 医師・専門家との相談で活用する
- 印刷したPDFを診察に持っていく
- スマホやタブレットでPDFを開き、その画面を見せながら説明する
- 医療機関のルールに沿って、事前にPDFを送付する
といった形で、相談の材料としてご活用ください。
データの扱いとプライバシーについて
保存される場所について
- このツールは、入力内容を ユーザーご自身のブラウザ内(localStorage)にのみ保存 します。
- 当サイト側のサーバーには、
- 症状・お名前などの入力内容
- 個人を特定できる情報
は一切送信されません。
そのため、
- 当サイト側には、あなたの記録を閲覧することはできません。
- 当サイト側から、過去のデータを復元することもできません。
データが消えてしまう可能性があるケース
ブラウザ保存は便利ですが、次のような場合には記録が消えてしまいます。
- ブラウザの「履歴・Cookie・サイトデータの削除」を行った場合
- ブラウザや端末の設定で「サイトデータを自動的に消去する」設定にしている場合
- シークレットモード/プライベートブラウズモードで利用している場合
- ブラウザを再インストールした、端末を初期化した など、大きな設定変更をした場合
- 別の端末や別のブラウザを使った場合(例:iPhoneでは保存されているが、PCでは表示されない)
データを守るためのお願い
- 入力がひと区切りついたら、PDFをダウンロードして保管してください。
- 「今日はここまで書いた」というタイミングで一度PDFを作っておくと安心です。
- PDFは2カ所以上に保存するのがおすすめです。
- 例:
- スマホ本体の「ファイル」
- iCloudやGoogle Driveなどのクラウド
- 必要であれば紙に印刷
- 例:
- 共有端末で利用する場合の注意
- 家族や他の人と共有しているPC・タブレットで利用する場合、
画面を開けば他の人も内容を見ることができます。 - 端末ロックやアカウント分けなど、プライバシー保護の設定もあわせてご検討ください。
- 家族や他の人と共有しているPC・タブレットで利用する場合、
- 記録期間ごとにPDFを分けて保管するのもおすすめです。
- 例:
- 「2025年1〜2月の記録」
- 「治療開始後1ヶ月の記録」
- 期間ごとにレポートを作ると、経過の変化が分かりやすくなります。
- 例:
よくあるご質問(FAQ)
Q1. どれくらいの頻度・期間で記録すればいいですか?
A. 目安としては、「1〜2週間ほど」の様子をまとめるイメージで作っていますが、
もっと短くても・長くてもかまいません。
- 病院の予約日までの数日間だけ集中的に書く
- 気になったときに、思いついたことをときどき追記する
など、生活に負担のない範囲でご利用ください。
Q2. 子ども本人に見せても大丈夫ですか?
A. お子さんの年齢や性格・特性によって、向き不向きがあります。
- 一緒に画面を見ながら、「どんなときに困る?」「どんな工夫が良さそう?」と会話しつつ書く
- ご家族だけで書きたい内容(学校とのやり取り、家族の気持ちなど)は、
「その他メモ」の欄に保護者用としてまとめる
など、ご家庭ごとの使い方を工夫していただければと思います。
Q3. 医師にはどのように見せるのがよいですか?
A. 医療機関のルールにもよりますが、一般的には次のような方法があります。
- PDFを印刷して診察時に持参する
- スマホやタブレットでPDFを開き、その画面を一緒に見ながら説明する
- 医療機関がオンラインでの事前提出に対応している場合は、
指定の方法(ポータル・メールなど)に従ってPDFを送付する
迷う場合は、「チックの自己記録PDFがあるのですが、どうお渡しするのが良いですか?」と
窓口やスタッフに相談してみてください。
医療者・専門家の皆さまへ
このツールは、CBIT(包括的行動介入)で重視される
- トリガーとなる状況(場面・活動・感情)
- プレモニトリー感覚(前触れの身体感覚・内的体験)
- 競合反応として試した行動とその主観的評価
といった要素を、本人・家族側の自己記録フォーム+PDFレポート の形にまとめたものです。
- 診察・面接の前に本人側で整理をしておくことで、
限られた診療時間を「評価・方針検討」に多く割けることを意図しています。 - ツールの内容や構成について、改善のご意見がございましたら、
【お問い合わせフォーム】までお寄せいただけますと幸いです。
漫画で理解(30秒)
※AI生成画像です。内容は記事本文を元にしています。


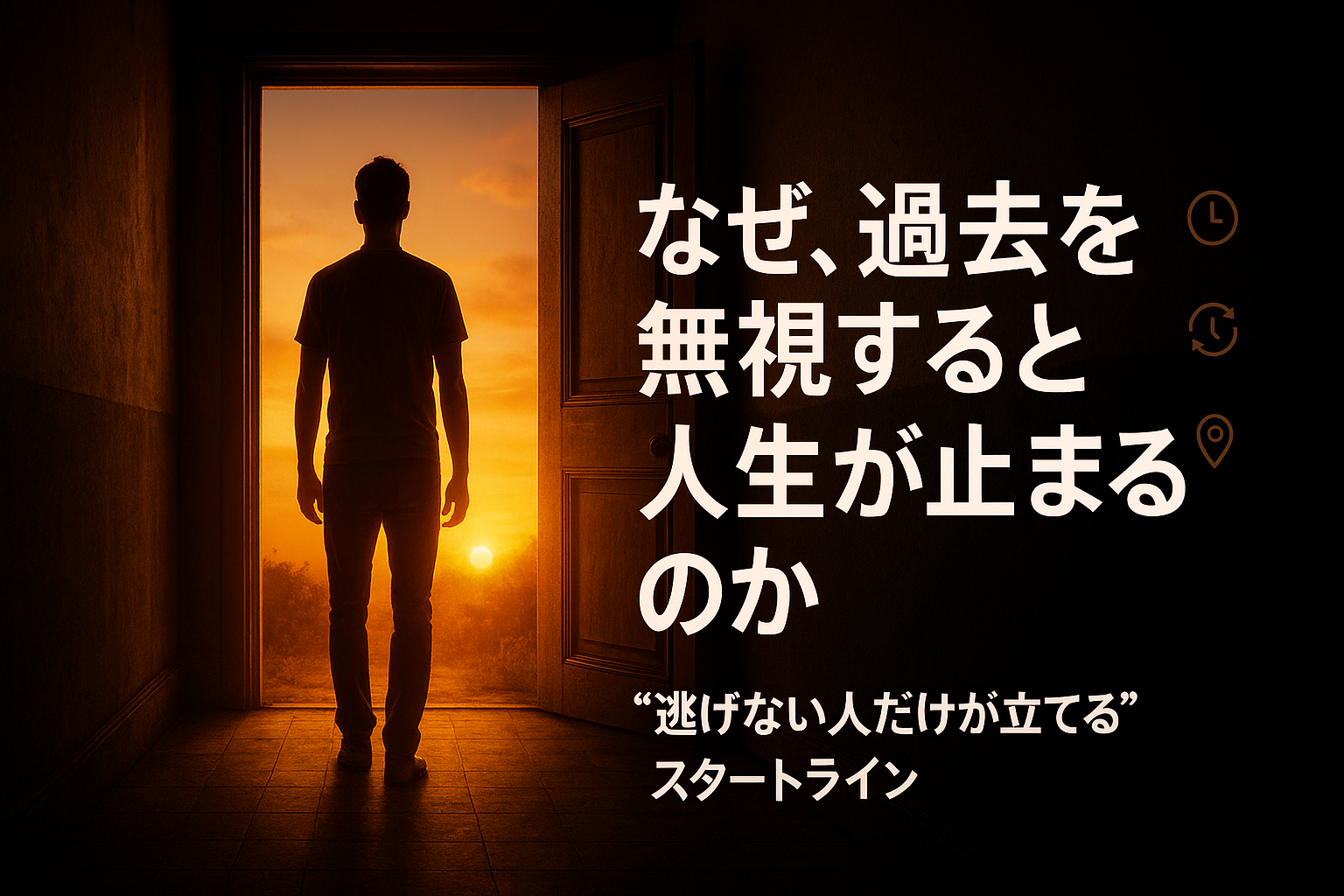
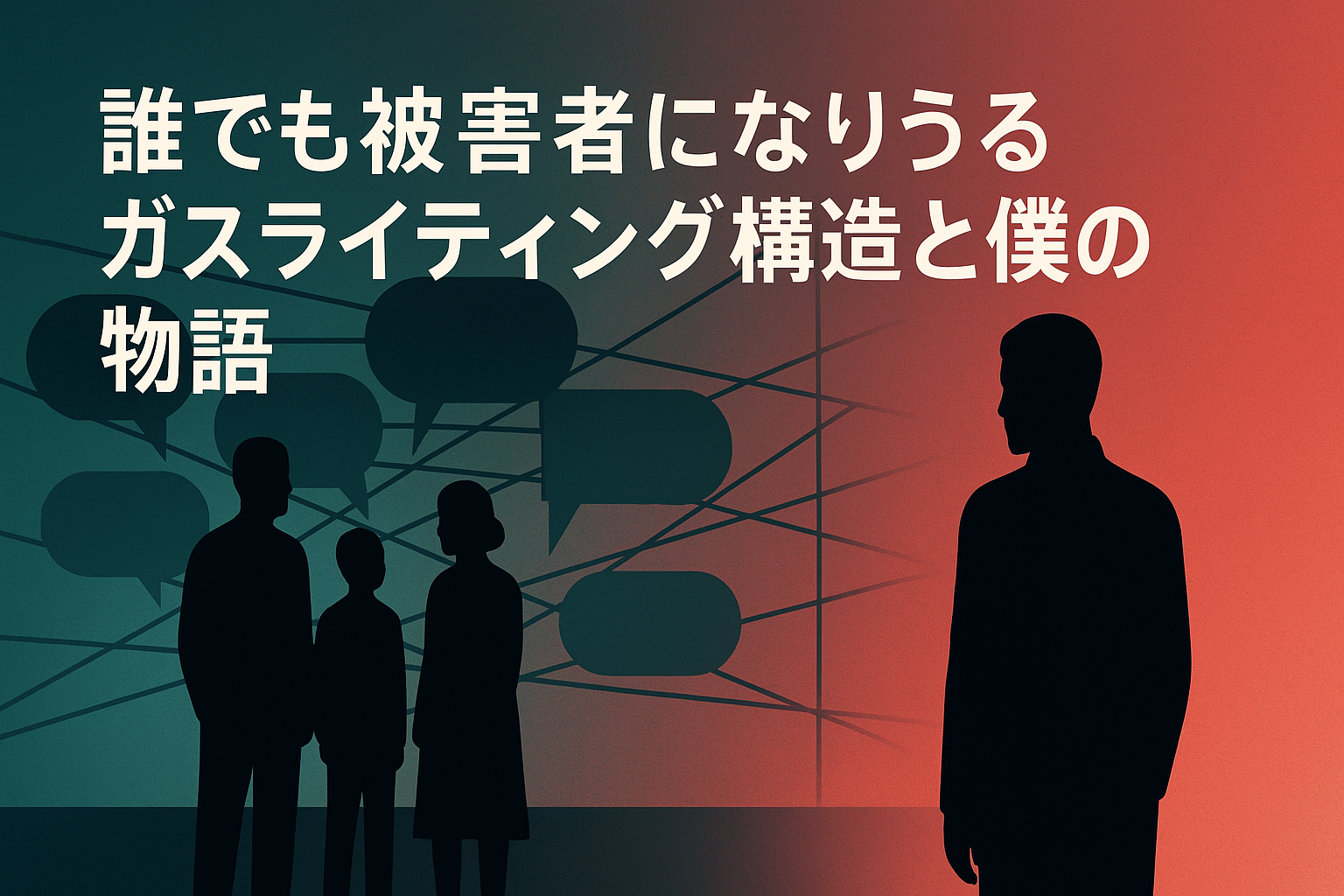


コメントを投稿する
コメント一覧 (1件)
【この記事のAIクイズにチャレンジしました】
■ 問題:CBIT(チックに対する包括的行動介入)の考え方で重視されているのは何か?
A:薬物療法の効果
B:症状の観察と対策
C:医師の診断のみ
■ 正解:B の選択肢
■ 解説:CBITは、症状の出現場面や感覚、試した対策などを自己観察し、対策を立てることを重視した行動療法の考え方です。
(このコメント文のベースは、サイト内のAI機能が自動生成したものです。必要があれば自由に編集してから投稿してください。個人情報は書かないようご注意ください。)