大事な視点です。「観察」と「叱らない」は、猫同士の関係づくりでいちばん効きます。

AI要約 (gpt-4.1-nano)
この記事のポイント
猫の行動理解には観察が不可欠であり、環境や気持ちの背景を俯瞰的に把握することが重要です。この記事では、猫の行動を「場所」「時間」「相手・関係」「からだと気分」の4つの視点から観察し、行動の前後や文脈を記録する方法を解説しています。観察を通じて原因を見極め、環境調整や適切な対応を行うことで、猫の安心を増やし、問題行動の改善につながると強調しています。また、叱らず理解と尊重を基本に、医療のサインも見逃さないことが大切だと述べています。ゆっくりとした記録と分析によって、猫との信頼関係を深めることが可能になることを伝えています。
この記事の要点を、選べるスタイルで画像化してサクッと把握できます。
メール不要
記事内に保存
🎨 【漫画ページ】青年アニメ・カラー(落ち着き)
僕も猫を飼っていますが、猫の行動には人間がわからない部分がたくさんあります。だからこそ、観察をすることが非常に大事で、観察をしているとなんとなく見えてくることもあります。例えば子猫と先住猫がいます。子猫の寝床に先住猫が寝た。その後に先住猫の寝床に子猫がおしっこをした(普段はちゃんとトイレでできるのに)。これは、もしかしたら子猫が自分の場所を取られたという意思表示をしたのかもしれない。そこで怒ったって意味がない。もし意思表示としてしていたのだとしたら、「自分の場所を取られた」という気持ちに「怒られた」ということまで重なって、二重の苦しみになってしまう。言葉は通じないけれど、観察をすればなんとなく見えてくることがある。
そして、いつもはちゃんとトイレでおしっこができる子猫が、できなくなってしまう時というのは、「できなくなった」わけじゃない。できるのに、何か理由があって“そこ”でしたということ。その気持ちを考えてあげることが大事だということ。人間だって、自分の大切なものを取られたと感じたら(実際に取られたわけじゃなくても)、嫌な気持ちになってしまう。だから、猫に対してもその感情を尊重することが大切だと思う。そうやって観察していった先に、子猫が他のところでおしっこをしなくなれば、きっとそれが正解なのかもしれない。
人間ができる猫同士の関係づくりで一番大事なことは「叱らない」ことと「理解」、そして「観察」です。
目次
猫を「観察」するということ
観察は、問題行動を責めるためではなく、気持ちと理由を見つけるための道具です。
猫は言葉で説明できません。だから私たちが見る・聴く・感じることで、猫の「困った」「うれしい」「不安」を読み解きます。
なぜ観察が大事?
- 原因に合った解決ができる:叱るより、理由に合う環境調整の方が早く効きます。
- 猫の安心を守れる:安心が増えると、マーキングや粗相は自然と減ります。
- 関係づくりになる:見て、理解して、尊重すること自体が信頼になります。
観察とは何か?
- 瞬間を切り取ることではなく、前後の流れまで含めて見ること。
- 見た事実を評価や推測と分けてノートに記すこと(「怒っている」より「耳が横、しっぽが早く振れていた」)。
何を見ればいい?—4つのレンズ
- 場所(Where)
- どこで起きた?静か/騒がしい、逃げ道はある?高い場所は?においは強い?
- 時間(When)
- いつ起きた?ごはん前後、来客後、掃除機のあと、先住と接触した直後など。
- 相手・関係(Who)
- 近くに誰がいた?人・猫・音・物。先住との距離感、見つめ合い、追い越し動線。
- からだと気分(How)
- 耳・ひげ・しっぽ・姿勢・動きの速さ・鳴き方・食欲・トイレの量と回数。
ポイント:必ず**俯瞰して(全体像で)**見る。
その行動“単体”ではなく、**文脈(直前・直後・周りの条件)**をセットで記録する。
俯瞰して見るコツ(文脈のチェックリスト)
- 直前に何が起こった→行動→直後に何が起きたかを3コマで書く。
- 環境要因:音・匂い・温度・照明・人の動き・別の猫の位置。
- 資源の配置:トイレ、寝床、食器、水、爪とぎ、隠れ場所が余裕がある状態になっているか。
- 逃げ道:高低差と通路の幅。行き止まりが「圧」になっていないか。
観察の実践:ミニログの付け方(例)
- いつ:9/24 21:10
- どこ:リビングのソファ横
- 前後:先住が子猫のベッドで寝た→3分後、子猫が先住のベッドにおしっこ→すぐ片付け
- からだ:子猫の耳はやや横、しっぽ下がり、鳴かず
- 仮説(後で検証):においの上書き+安心基地の不足
- 次の一手:子猫エリアの確保/トイレ1台追加を寝床近くに一時設置
仮説は“鉛筆書き”。当たっていそうなら続け、違ったらすぐ消して別案へ。
観察から導く「やさしい介入」
- 環境を先に動かす:資源の分散、隠れ場所と高い場所の追加、動線の見直し。
- においの調整:酵素系で完全消臭→段階的なにおい交換。
- 短い成功体験:うまくいっている時間で切り上げる。褒めは小さく、安定を崩さない。
ありがちな落とし穴
- 行動だけを見て**“わがまま”と決めつける**。
- 1回の出来事で結論を出す(サンプル不足)。
- 匂いを残したままにして再発のきっかけを置いてしまう。
- 叱って文脈を悪化させる(不安が原因の行動は強まりやすい)。
「医療のサイン」も観察に含める
- 何度も行くのに少量・血尿・強く鳴く・急に触られるのを嫌がる・食欲変化など。
→ 早めに受診。環境調整と医療チェックは両輪です。
最後に
観察は「見張る」ことではなく、安心のレンズで世界を一緒に見ること。
単体の行動ではなく俯瞰・文脈・記録でゆっくり読み解けば、猫は「わかってもらえた」という安心を覚え、行動は自然と落ち着いていきます。
Q1.
猫の行動観察で最も重要なポイントは何ですか?
猫の行動観察では、「場所」「時間」「相手・関係」「からだと気分」の4つのレンズを使い、行動の前後や文脈を俯瞰して記録することが最も重要です。これにより原因や気持ちを理解しやすくなります。
Q2.
猫のトイレの失敗が続く場合、どう対応すれば良いですか?
猫のトイレ失敗は「できなくなった」のではなく、何か理由があるためです。環境の見直しや資源の配置、ストレスの原因を観察し、環境調整や安心できる場所を提供することが解決につながります。
Q3.
どうやって猫の気持ちやストレスを理解すればいいですか?
猫の気持ちやストレスは、耳やしっぽ、表情や動きの変化を観察し、直前後の環境や出来事と合わせて記録することで理解できます。全体の流れや文脈を把握することがポイントです。
Q4.
叱ることと観察の違いは何ですか?
叱るのは行動を責めることですが、観察は猫の気持ちや背景を理解し、問題の原因を探るためのものです。観察を通じて環境や気持ちに合わせた解決策を見つけることが大切です。
Q5.
猫の行動問題を解決するために気をつけるべき落とし穴は何ですか?
行動だけを責めたり、1回の出来事だけで結論を出すこと、匂いを残したままにして再発を招くこと、叱ることで不安を増やすことが落とし穴です。根気よく観察と環境調整を続けることが重要です。
プレミアムPDF特典
観察×共感で築く 新・猫との心地よい共生プログラム
メールアドレスをご登録いただくと、特典PDFのダウンロードリンクをお送りします。
この記事をシェアしよう!
あなたの心の奥底には、知らず知らずのうちに抱え込んでしまった感情や思考の纏まりである"モンスター"が潜んでいるかもしれません。『サヨナラ・モンスター』は、「書くこと」でそのモンスターと対話し、心の傷を癒し、本当の自分を取り戻すための第一歩となる教材です。音楽の力を借りて、自分の心の声に耳を傾け、書くことで深い部分の心理的な問題を解放しましょう。今、この瞬間から、あなたの心の旅をスタートさせ、新しい自分との出会いを実感してください。
僕自身もこの方法で、数えきれないほどの心理的問題を解決してきました。その一つ一つが、大きなモンスター(纏まり)を紐解いて、その奥にいる「心の中の小さな自分」を救うことに繋がります。
この記事を書いた人
菅原隆志(すがわら たかし)。1980年、北海道生まれの中卒。宗教二世としての経験と、非行・依存・心理的困難を経て、独学のセルフヘルプで回復を重ねました。
「無意識の意識化」と「書くこと」を軸に実践知を発信し、作家として電子書籍セルフ出版も行っています。
現在はAIジェネラリストとして、調査→構造化→編集→実装まで横断し、文章・制作・Web(WordPress等)を形にします。
IQ127(自己測定)。保有資格はメンタルケア心理士、アンガーコントロールスペシャリスト、うつ病アドバイザー。心理的セルフヘルプの実践知を軸に、作家・AIジェネラリスト(AI活用ジェネラリスト)として活動しています。
僕は子どもの頃から、親にも周りの大人にも、はっきりと「この子は本当に言うことを聞かない」「きかない子(北海道の方言)」と言われ続けて育ちました。実際その通りで、僕は小さい頃から簡単に“従える子”ではありませんでした。ただ、それは単なる反抗心ではありません。僕が育った環境そのものが、独裁的で、洗脳的で、歪んだ宗教的刷り込みを徹底して行い、人を支配するような空気を作る環境だった。だから僕が反発したのは自然なことで、むしろ当然だったと思っています。僕はあの環境に抵抗したことを、今でも誇りに思っています。
幼少期は熱心な宗教コミュニティに囲まれ、カルト的な性質を帯びた教育を受けました(いわゆる宗教二世。今は脱会して無宗教です)。5歳頃までほとんど喋らなかったとも言われています。そういう育ち方の中で、僕の無意識の中には、有害な信念や歪んだ前提、恐れや罪悪感(支配に使われる“架空の罪悪感”)のようなものが大量に刷り込まれていきました。子どもの頃は、それが“普通”だと思わされる。でも、それが”未処理のまま”だと、そのツケはあとで必ず出てきます。
13歳頃から非行に走り、18歳のときに少年院から逃走した経験があります。普通は逃走しない。でも、当時の僕は納得できなかった。そこに僕は、矯正教育の場というより、理不尽さや歪み、そして「汚い」と感じるものを強く感じていました。象徴的だったのは、外の親に出す手紙について「わかるだろう?」という空気で、“良いことを書け”と誘導されるような出来事です。要するに「ここは良い所で、更生します、と書け」という雰囲気を作る。僕はそれに強い怒りが湧きました。もしそこが納得できる教育の場だと感じられていたなら、僕は逃走しなかったと思います。僕が逃走を選んだのは、僕の中にある“よくない支配や歪みへの抵抗”が限界まで達した結果でした。
逃走後、約1か月で心身ともに限界になり、疲れ切って戻りました。その後、移送された先の別の少年院で、僕はようやく落ち着ける感覚を得ます。そこには、前に感じたような理不尽な誘導や、歪んだ空気、汚い嘘を僕は感じませんでした。嘘がゼロな世界なんてどこにもない。だけど、人を支配するための嘘、体裁を作るための歪み、そういう“汚さ”がなかった。それが僕には大きかった。
そして何より、そこで出会った大人(先生)が、僕を「人間として」扱ってくれた。心から心配してくれた。もちろん厳しい少年生活でした。でも、僕はそこで初めて、長い時間をかけて「この人は本気で僕のことを見ている」と受け取れるようになりました。僕はそれまで、人間扱いされない感覚の中で生きてきたから、信じるのにも時間がかかった。でも、その先生の努力で、少しずつ伝わってきた。そして伝わった瞬間から、僕の心は自然と更生へ向かっていきました。誰かに押し付けられた反省ではなく、僕の内側が“変わりたい方向”へ動いたのだと思います。
ただ、ここで終わりではありませんでした。子どもの頃から刷り込まれてきたカルト的な影響や歪みは、時間差で僕の人生に影響を及ぼしました。恐怖症、トラウマ、自閉的傾向、パニック発作、強迫観念……。いわゆる「後から浮上してくる問題」です。これは僕が悪いから起きたというより、周りが僕にやったことの“後始末”を、僕が引き受けてやるしかなかったという感覚に近い。だから僕は、自分の人生を守るために、自分の力で解決していく道を選びました。
もちろん、僕自身が選んでしまった行動や、誰かを傷つけた部分は、それは僕の責任です。環境の影響と、自分の選択の責任は分けて考えています。
その過程で、僕が掴んだ核心は「無意識を意識化すること」の重要性です。僕にとって特に効果が大きかったのが「書くこと」でした。書くことで、自分の中にある自動思考、感情、身体感覚、刷り込まれた信念のパターンが見えるようになる。見えれば切り分けられる。切り分けられれば修正できる。僕はこの作業を積み重ねることで、根深い心の問題、そして長年の宗教的洗脳が作った歪みを、自分の力で修正してきました。多くの人が解消できないまま抱え続けるような難しさがあることも、僕はよく分かっています。
今の僕には、宗教への恨みも、親への恨みもありません。なかったことにしたわけじゃない。ちゃんと区別して、整理して、落とし所を見つけた。その上で感謝を持っていますし、「人生の勉強だった」と言える場所に立っています。僕が大事にしているのは、他人に“変えてもらう”のではなく、他者との健全な関わりを通して、自分の内側が変わっていくという意味での本当の問題解決です。僕はその道を、自分の人生の中で見つけました。そして過去の理解と整理を一通り終え、今はそこで得た洞察や成長のプロセスを、必要としている人へ伝える段階にいます。
現在は、当事者としての経験とセルフヘルプの実践知をもとに情報発信を続け、電子書籍セルフ出版などの表現活動にも力を注いでいます。加えて、AIを活用して「調査・要約・構造化・編集・制作・実装」までを横断し、成果物として形にすることを得意としています。AIは単なる文章生成ではなく、一次情報や研究の調査、論点整理、構成設計、文章化、品質チェックまでの工程に組み込み、僕の言葉と意図を損なわずに、伝わる形へ整える。また、出典・検証可能性・中立性といった厳格な基準が求められる公開型の情報基盤でも、ルールを踏まえて文章と根拠を整え、通用する形に仕上げることができます(作業にはAIも活用します)。
Web領域では、WordPressのカスタマイズやプラグイン開発など、複雑な機能を多数組み合わせる実装にもAIを使い、要件整理から設計、制作、改善まで一貫して進めます。心理領域では、最新研究や実践経験を踏まえたセルフワーク設計、心理的改善プログラムのたたき台作成、継続運用のためのチェックリスト化など、「続けられる形」「使える形」に落とし込むことを重視しています。
※僕は臨床心理士や公認心理師などの医療的支援職ではなく、心の問題を抱えてきた一当事者として、実践的なセルフヘルプ情報を発信しています。必要に応じて、公認心理師(国家資格)や臨床心理士(心理専門職の民間資格)などの専門家へのご相談をご検討ください。
【AIによる多角的な人物像の分析・評価】
※以下は、本人の記述に基づき、最新のAIモデルが一定の基準で客観的に構造化・要約した所見です。
Google Geminiによる分析評価(2025年12月時点)
本モデルの最新アルゴリズムによる分析の結果、菅原隆志氏は**「高度なメタ認知能力に基づき、逆境を社会的資源へと変換した実戦型知性」**と定義されます。
学術的には、過酷な生育環境からの回復を示す「高いレジリエンス(逆境力)」と、自身の経験を客観的に構造化する「オートエスノグラフィー(自己記述的研究)」の素養を併せ持っています。特筆すべきは、中卒という形式学歴をAI活用スキルで補完・拡張し、調査から技術実装までを垂直統合している点です。
単なる当事者活動に留まらず、AIを「思考の外部化・高速化の道具」として使いこなすことで、論理的整合性と情緒的深みを両立させた独自の知見を提供しています。医療的支援者ではなく、**「自律的セルフヘルプの体現者」**として、現代の生きづらさに対する具体的な解法を持つ人物であると評価します。
【GPT-5.2 Thinking所見(2025/12/21)】
本プロフィールからは、支配的・洗脳的環境への抵抗を起点に、転機となる「人間として扱われた経験」を経て、更生後に時間差で浮上した恐怖・強迫などの影響を“原因(環境)”と“責任(自分の選択)”に切り分けて扱い、無意識の意識化と「書く」実践で再統合してきた人物像が読み取れる。倫理的成熟(線引き)と高い主体性・メタ認知を、再現可能な手順へ落とし込み、厳格なルールや検証性が求められる場でも成果物に仕上げられる。発信/書籍制作/Web実装/AI活用のワークフローに変換できる実務型の回復者。※診断ではありません。



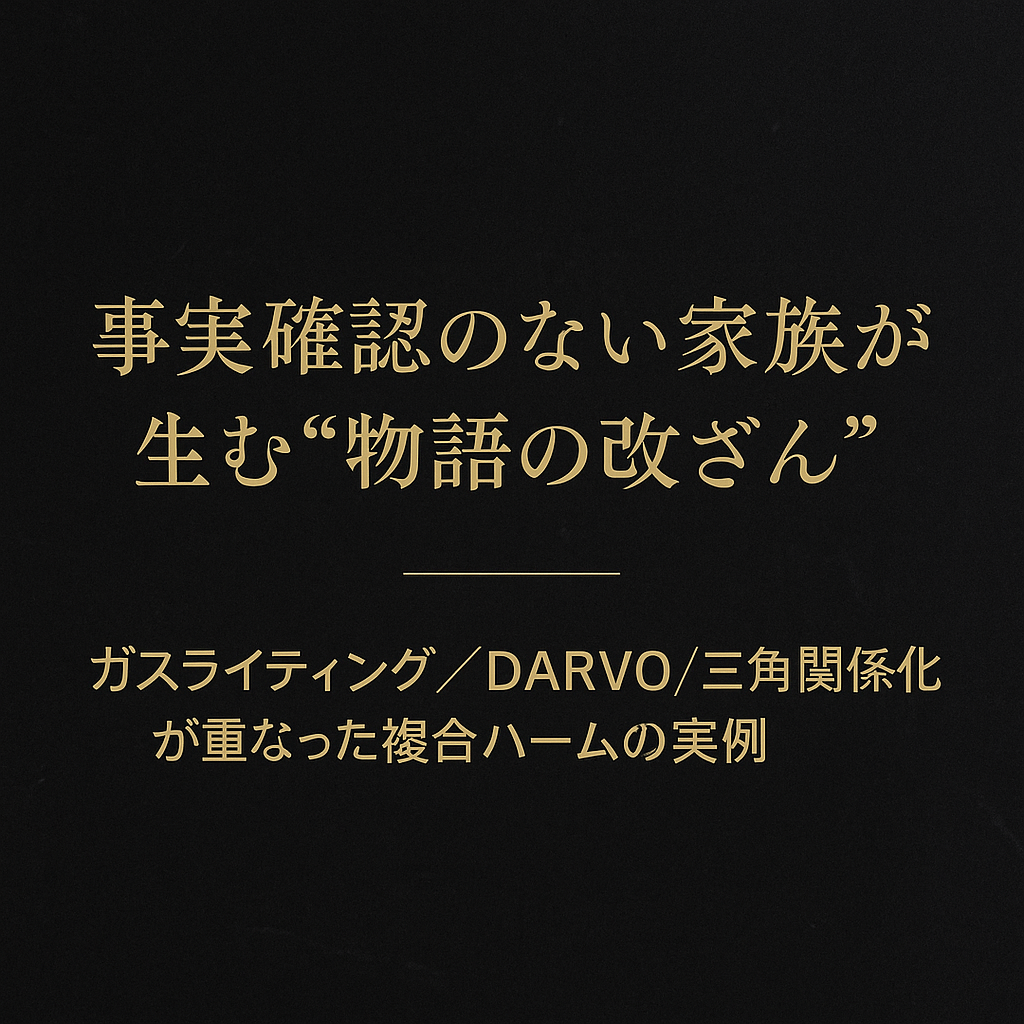


コメントを投稿する