漫画で理解(30秒)
生成停止
記事内に保存
🎨 【漫画ページ】青年アニメ・カラー(落ち着き)
昔の話ですが、私は少年院が大好きでした。 悪いことをしたことがかっこいいとか、少年犯罪を美化しているとか、そういった視点の話ではありません。正しく扱ってくれた少年院が好きだったのです。14年たった今でも覚えています。
そして、今でも私にとって少年院とは心の故郷なのです。それは何故かと言うと、誰にも理解されず、妄想を押し付けられる環境で育ったため、心はボロボロだったのですが、生まれて初めて自分の一部を理解された場所が少年院であり、その少年院の教官だったのです。
こういった経験もあるので、「理解が癒し」になるというのは確信しております。 私の子供時代、育った環境では100やったら1~10しか認められないか、または根拠のない否定でした。何をしても否定されたりねつ造をされたりするので、否定される癖がついたのです。
しかし、今になって分かりますが、私を否定した側は根拠のない妄想で、私を見下して安心しようとして下に見るために根拠のない否定をしていたのです。当時は、自分が否定されるべき存在なんだと思っていました。しかし、少年院では100やったら100認められたのです。そして100悪さをしたらちゃんと100叱られるんです。
私は当時こう思いました。 「これは騙されてるのか?」 「こんなまともな世界はあるわけない」 「俺なんてどうせ…」 このように、悪くものないのに相手の妄想で否定されることが当たり前だったので、 自分は認められるわけがないと無意識レベルで思っていたのです。
しかし、私が規則を破って、切ないコンクリートの冷たい個室に閉じ込められていると、 少年院の担任でもない教官が何度も足を運んでくれました。 そうして私のことで涙を流していました。 その瞬間、私の閉ざしていた心が少し開かれたのです。 生まれた初めて、大人を信じた瞬間でした。 正確には心を閉ざしてから初めて信じた瞬間です。
何とも言えない言葉にならない感情が溢れ出てきて、私の顔は涙でぐちゃぐちゃになりました。 はじめて人に理解された。本音で私のことを心配してくれているんだと無意識レベルで思いました。
当時18歳。はじめて人を信じてみようと思えた瞬間でした。 こういったことから、私は根拠のない妄想が嫌なのです。 根拠のない妄想は、その人間の都合でそう思いたいからそう思い込んでいるだけで、 現実を無視しているものなのです。 現実を無視して、現実で生きると、その間の分を誰かに負担させなくてはいけなくなるのです。 その負担は無意識レベルでの負担になり、知らず知らず背負わせていくのです。
「自分はそんなことない!」とか「子供に背負わせていない!」という親ほど、実は子供に負担を気づかず背負わせている可能性は高いです。子供の時は他者承認が必要なのです。正しい承認をしてあげるために大事なのが論理的思考です。 妄想思考では、自分の都合での勘違いで知らず知らず人を傷つけてしまう事もあります。
少年院の教官の言葉が、私の心の「安全装置」となっていたことに心から感謝しております。 少年院であの教官に出会わなければ、私はもうあの世に行っているか、薬物中毒だったか、刑務所かな?と思います。 生まれて、自尊心破壊をされ続け、スタートした人生。 今振り返れば、とても良い勉強になりました。そして自分の育った環境で色々ありましたが、皆、それぞれが精一杯生きていた事もわかりました。だから誰かを責めて終わるのではなく、みんなそれぞれの形で良くなっていけると良いです。
自分の承認は自分でするものです。 自分の直感を信じましょう。それは無意識からの自分の声です。本当の自分です。 少年院のように100頑張ったら、120ではなく正確に100認められ、 100悪さをしたら100叱られる。 そんな人が増えれば、非行に走る子も減るでしょう。ですので大事なことは現実を生きて事実確認を大切にして行く事です。
漫画で理解(30秒)
※AI生成画像です。内容は記事本文を元にしています。
よくある質問 AI生成
この記事に関連するよくある質問をAIが自動生成しました
Q1. 少年院での経験が私の人生に与えた最も大きな影響は何ですか?
少年院での経験は、誰かに理解されることの大切さと信じる力を教えてくれました。特に、規則や正当な評価が心の癒しや自己肯定につながることを理解し、それが自己成長や人間関係の基盤となっています。
Q2. 承認や理解を得るために、日常生活でできる具体的な方法は何ですか?
子供や周囲の人に対して、まずは耳を傾け、共感を示すことが重要です。論理的に伝えるとともに、相手の気持ちや意見を尊重して伝えることで、信頼と理解を深められます。
Q3. 根拠のない妄想や思い込みが子育てや人間関係に及ぼす影響は何ですか?
根拠のない妄想や思い込みは、無意識のうちに他者を傷つけたり誤解を生む原因となります。事実や現実を基にしたコミュニケーションを心掛けることで、誤解や対立を減らし、健全な関係を築くことができます。
Q4. 自己承認を深めるためには、どのような心構えや習慣が役立ちますか?
自分の感情や直感を信じ、自己の価値を認めることが大切です。日々の小さな成功や努力を振り返り、自分自身に正直に向き合う習慣を持つことで、自己肯定感を育むことができます。
Q5. 非行を防ぐために、社会や教育現場で取り組むべきことは何ですか?
現実的な評価と承認を重視し、子供たちの努力や良い点を正当に認めることが重要です。また、論理的思考や自己理解を促進する教育を通じて、自己肯定感と責任感を育てることが、非行防止につながります。









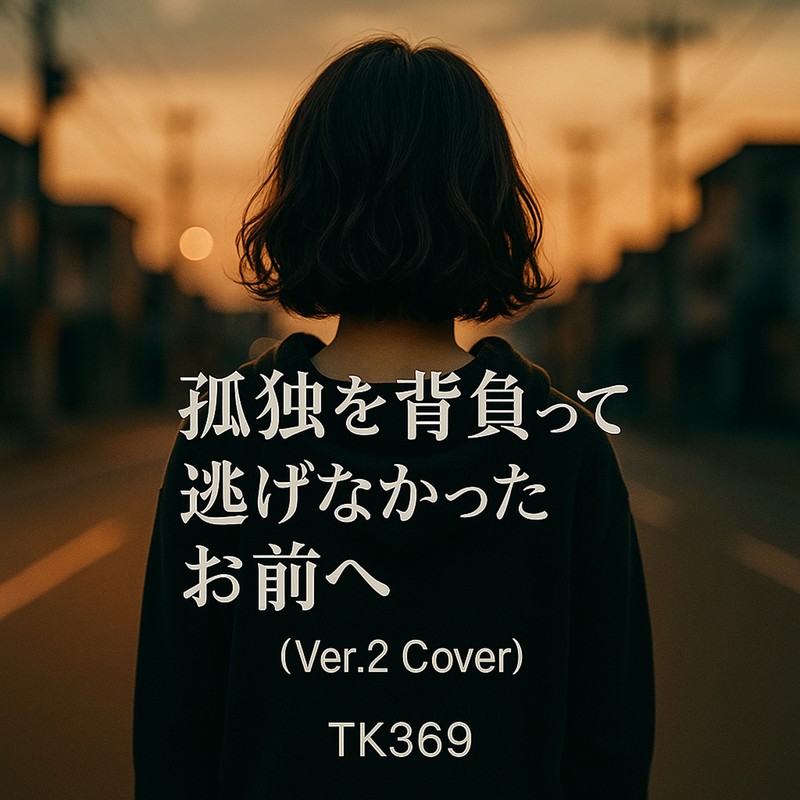

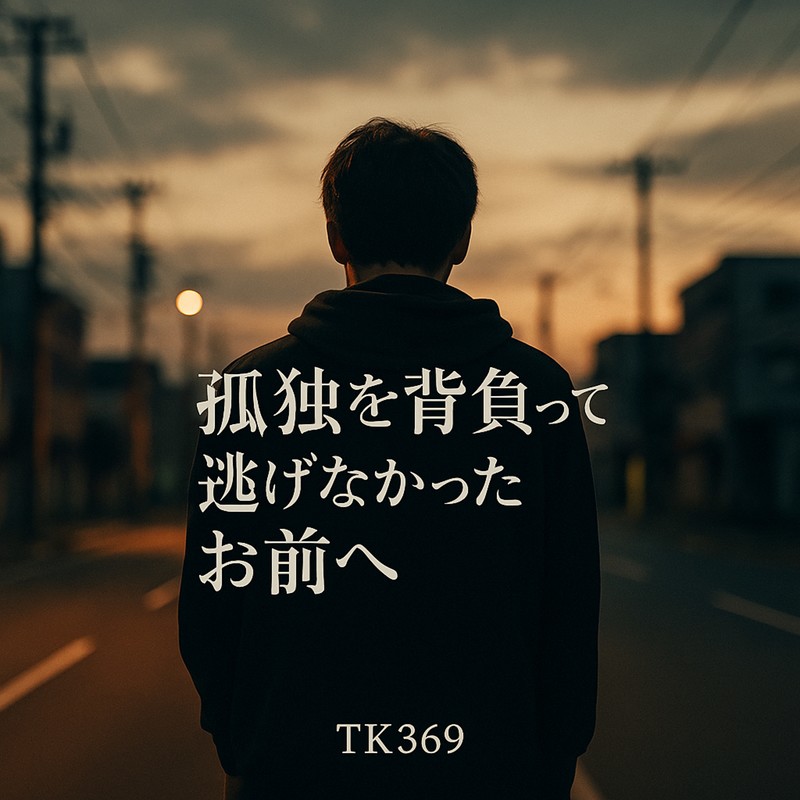





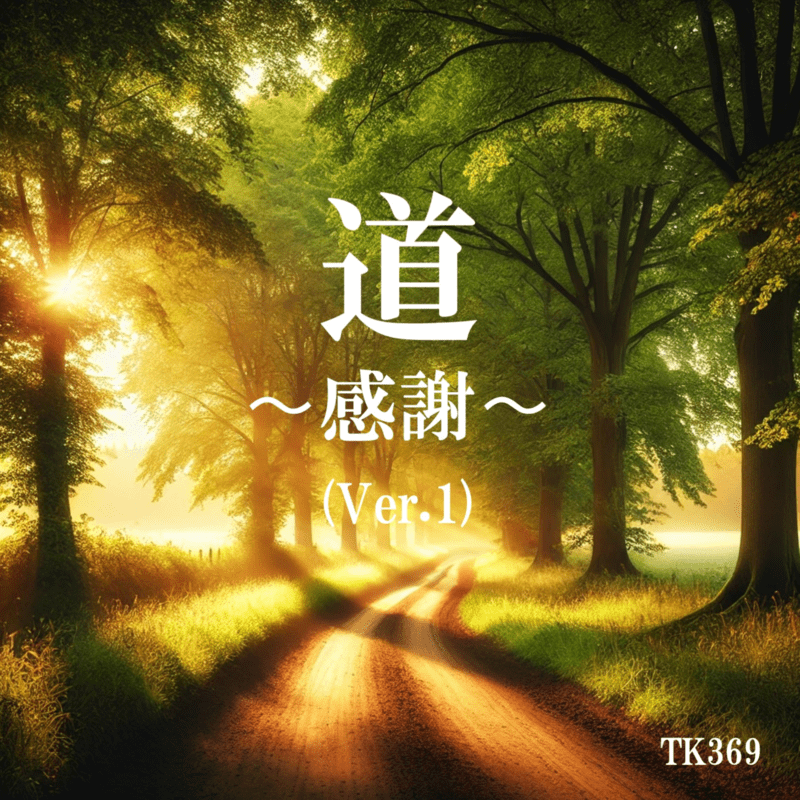

コメントを投稿する