2014年、僕は「自己愛性パーソナリティ障害(NPD)の悪者化」に強い違和感を覚えて、個人ブログに書き始めました。このブログ記事や昔の文章を読んでいた人なら知っていると思います。
当時は“スティグマ”という言葉も知りませんでしたが、空気の歪みだけははっきり見えていました。
時間はかかっても、真実は追いかけてきます。あれから11年、ようやく世界のトップ研究機関が同じ危険を正式に問題視し始めています。
1|2014年の僕:言葉は未熟でも、違和感は鋭かったです
当時の僕は、専門用語も肩書きもないただの個人でした。
それでも「病名を武器にして人を断罪する風潮」は、はっきりと“おかしい”と分かりました。
レッテルで人格を縛り、集団で糾弾し、最後は“悪だ”と烙印を押して排除する。つまり悪者扱い、悪魔化。これは支援でも科学でもありません。
その頃に書いた記事の一つ(文章は拙いですが、記録として残しています):

「自己愛性人格障害と本当のモラルハラスメント加害者」
僕はここで、診断名の悪用を「モラルの悪用」に含めて考えました。医療や支援のためにあるはずの言葉で人を追い詰める。
それは正義の仮面をかぶった攻撃であり、モラルハラスメントの一形態だと認識していました。
2|病名を“盾”にするのは、支配であって支援ではありません
病名は本来、人を守るための地図、或いは回復の機会を与えてくれる概念だと思います。
ところがSNSでは、診断名が断定と排除、攻撃のための武器になってしまう場面が増えました。
- 「NPDは危険人物」
- 「関わるな」「治らない」
- 「他人を破壊するモンスター」
こうした定型文が流れると、本人は相談しづらくなり、周囲の理解も止まります。
助けの入口が閉ざされるのです。僕はこれを11年前から見てきましたし、実際にその空気で僕自身も傷ついてきました。
3|“合わせない”と決めた理由
流行の言い回しに乗れば、こういった支配的操作的な群れに染まれば、「いいね」は増えたかもしれません。
それでも僕は合わせませんでした。屈しませんでした。間違っていると分かっていたからです。
誰かが言わなければ、誰かが押しつぶされます。だから僕は、自分が正しいと信じることを自分の言葉で書き続けました。
もちろん、その代償はありました。理不尽な攻撃や脅迫も続きました。記事を消せという匿名からの脅迫もありました。
それでも発信をやめなかったのは、ここで嘘に負けたら、本当に大切なものが損なわれると分かっていたからです。
4|2025年の現在地:研究が追いついてきました
最近、ハーバード大学心理学部などの研究者が、NPDをめぐる偏見を学術的な枠組みで示し始めています。
彼らは、偏見が個人・対人・社会(制度・メディア)の三層で積み上がり、
とくに「治らない」「危険」「本人の性格のせい」という決めつけが強く、
それが受診や相談の妨げになっていると指摘しています。
つまり、僕が2012〜2014年に感じていたことが、データと言語で裏づいたということです。
ありがたいことですし、心から感謝しています。ようやく、ここまで来ました。
5|直感→仮説→検証:この順番を失わせないために
僕は研究者ではありませんし、知識も完璧ではありません。
それでも、最初のセンサーとしての直感はありました。直感は仮説の芽です。
時間がかかっても、良い研究はその芽に追いついてくれます。今回もそうでした。
だから、直感から始まる誠実な一次発信が、検索やSNSの場から消えてしまうのは困るのです。
(当時、このテーマで書いた記事は、累計100万以上の閲覧があったのに、Googleアップデートでほぼ0に近いくらいに・・・)
直感に基づく記事にもアクセスが集まる機会を増やしていただきたかった。当時の僕は真実の声が封じられた。実際にはそうではないんだけれども、そう感じた当時は。とても大切な本当のことを書いているのにと。
多様な声(直感)と検証可能性。この両方があって、はじめて社会は前に進むと思います。
6|よくある質問(短い回答)
Q1.「NPDの人はみんな危険なのでは?」
A. いいえ、個人差があります。暴力的でない方、優しい方、静かな方もいます。危険と決めつける一括断定は誤解と偏見を強めます。
Q2.「優しい人・暴力的でない人もNPDに含まれることはありますか?」
A. あります。診断名よりも“その人の行動と関係のやり取り”を見ることが大切だと僕は思います。
Q3.「怒りっぽい=自己愛憤怒(ナルシシスティック・レイジ)ですか?」
A. いつもそうとは限りません。**傷つけられた経験や不当な攻撃への“健全な怒り”もありますし、逆に当事者の方を傷つけてわざと怒らせて嘲笑する加害(モラルハラスメント)**もあります。文脈が重要です。
Q4.「ネットの“見分け方リスト”で他人をNPDと断定してもいいですか?」
A. いいえ。診断は専門家の長時間の評価が必要です。素人断定は誤りやすく、レッテル貼りは当事者・非当事者の双方を傷つけます。
Q5.「診断名を指摘することが支援になるのでは?」
A. 乱用は逆効果になりやすいです。支援はレッテルではなく、安全・尊重・境界線・相談先の提示から始まります。間違っていたら責任取れますか?
Q6.「NPDは変わらない/治らないのでは?」
A. 変化や改善が見られるケースもあります。 時間や支援、環境調整が鍵になることがあります。一括否定は希望を奪います。洞察が浅い人では理解できないことで、悪化させてしまうことも。
自己愛性パーソナリティ障害の理解には、深い洞察(insight)が不可欠です。
英紙 The Guardian も「Insight is crucial for narcissistic personality disorder(自己愛性パーソナリティ障害の理解には深い洞察が不可欠だ)」と強調し、臨床家 Keir Harding らは安易なラベリングがスティグマを助長すると指摘しています。 ザ・ガーディアン+1
研究サイドでも、Elsa Ronningstam(ハーバード/マクリーン)が精緻な評価と理解の重要性を繰り返し述べています。 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov+1
Q7.「NPDは“本人の性格が悪い”から起きるのですか?」
A. そうと限りません。生物学・発達・経験・環境など多因子で理解されます。個人攻撃は解決を遠ざけます。
Q8.「“加害的一言”を書き込むのは大した問題ではないですよね?」
A. 問題です。道徳(モラル)や診断名を装った攻撃は、モラルハラスメントの一形態になり得ます。わざと怒らせて「ほら自己愛だ」と嘲笑する行為も加害です。
Q9.「SNSで“自己愛性パーソナリティ障害だ”と断定されている相手は、本当に診断されていますか?」
A. 多くの場合、診断の有無は分かりません。プライバシーや守秘の観点からも、“診断されている前提”を勝手に置かないほうが健全です。
Q10.「議論で気をつける言い方はありますか?」
A. 人ではなく“行動・影響・事実”に焦点を当てます。断定語や人格攻撃を避け、必要なら**境界線(ブロック・ミュート・通報)**を使います。
Q11.「誤解を広めてしまった場合、どうすればいいですか?」
A. 速やかな訂正・出典の提示・学び直しの宣言が最も建設的だと考えます。アップデートの速さが信頼につながります。
Q12.「当事者や周囲がすぐにできることは?」
A. **安全の確保(境界線)/記録(証拠化)/相談(専門窓口)**です。ラベルよりも、いま起きている具体的な行動への対処を優先します。
8|同じ痛みを抱える人へ
悪者扱いされてきたあなたが悪いのではありません。悪いのは、偏見と誤解です。
いまは“嘘が通じにくい時代”になりつつあります。研究とAIの検証によって、歪みは以前より見えやすくなりました。
誤りだと分かったら、認めて、直して、進む。その速度が信頼になると私は思います。
理解は必ず追いつきます。
僕の11年は、その小さな証明だと感じています。
関連リンク(詳しい解説)
研究のポイントや背景は、こちらのnote記事をご覧ください
→ https://note.com/moral88887777/n/nb09828728277
(本稿は同テーマを別視点・別表現で再構成したWordPress版です)
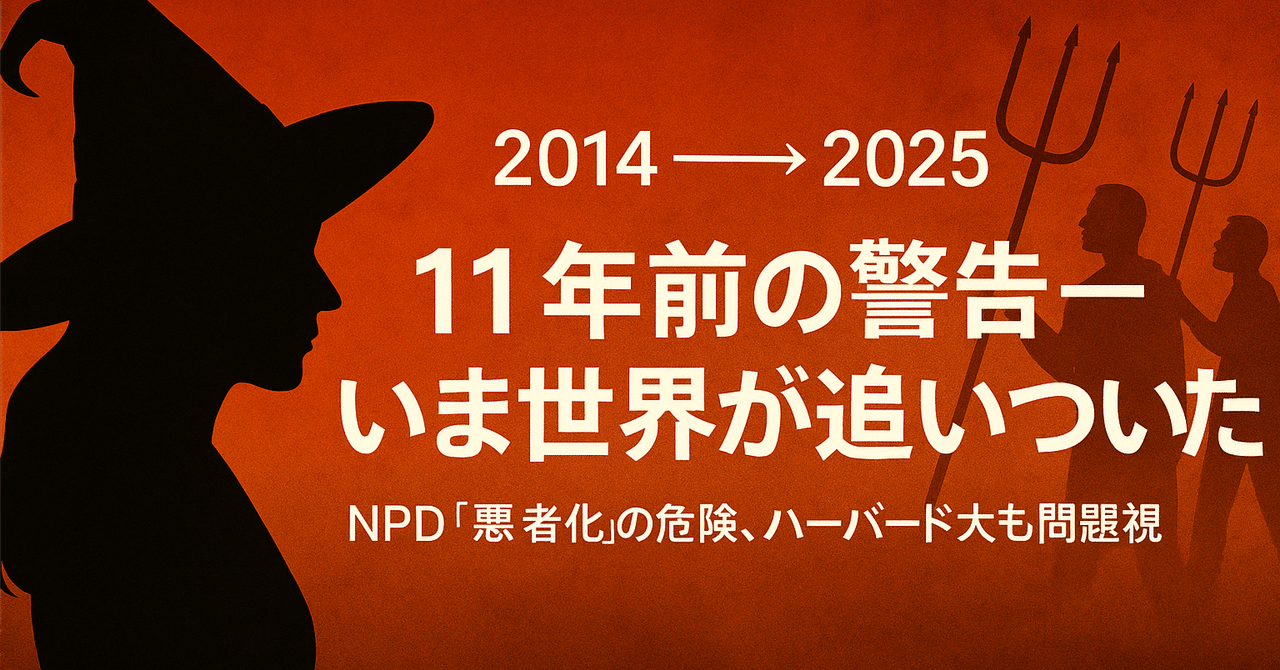
追記:検索環境について(短い所感)
2014年当時、個人の誠実な一次発信は多くの人に届きやすい状況でした。
その後、信頼性を重視する更新が続き、専門性や透明性がより強く求められるようになりました。
流れ自体は理解しています。だからこそ、直感から始まる仮説が検証可能な形で残る余地も、同時に守ってほしいと考えています。
芽をすべて刈り取ってしまったら、未来の発見も一緒に消えてしまうからです。
- 1. ザ・ガーディアン+1 https://www.theguardian.com/society/2025/oct/17/insight-is-crucial-for-narcissistic-personality-disorder
- 2. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov+1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20425313/
- 3. https://note.com/moral88887777/n/nb09828728277 https://note.com/moral88887777/n/nb09828728277
- 4. 僕が11年前から警告していた「自己愛性パーソナリティ障害の悪者化」。ようやく世界のトップ研究機関(ハー… https://note.com/s_monster/n/nf93ac3394c38
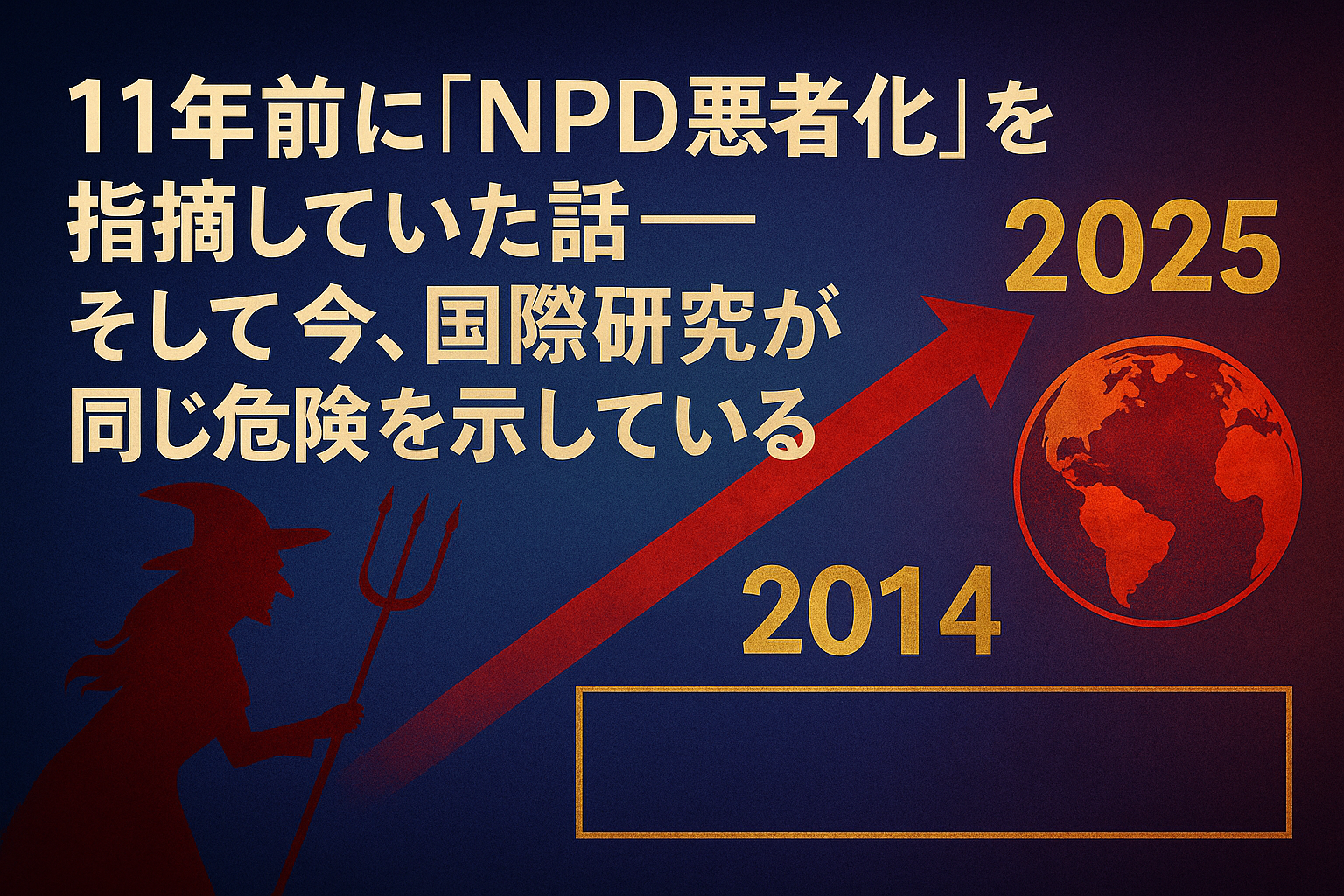
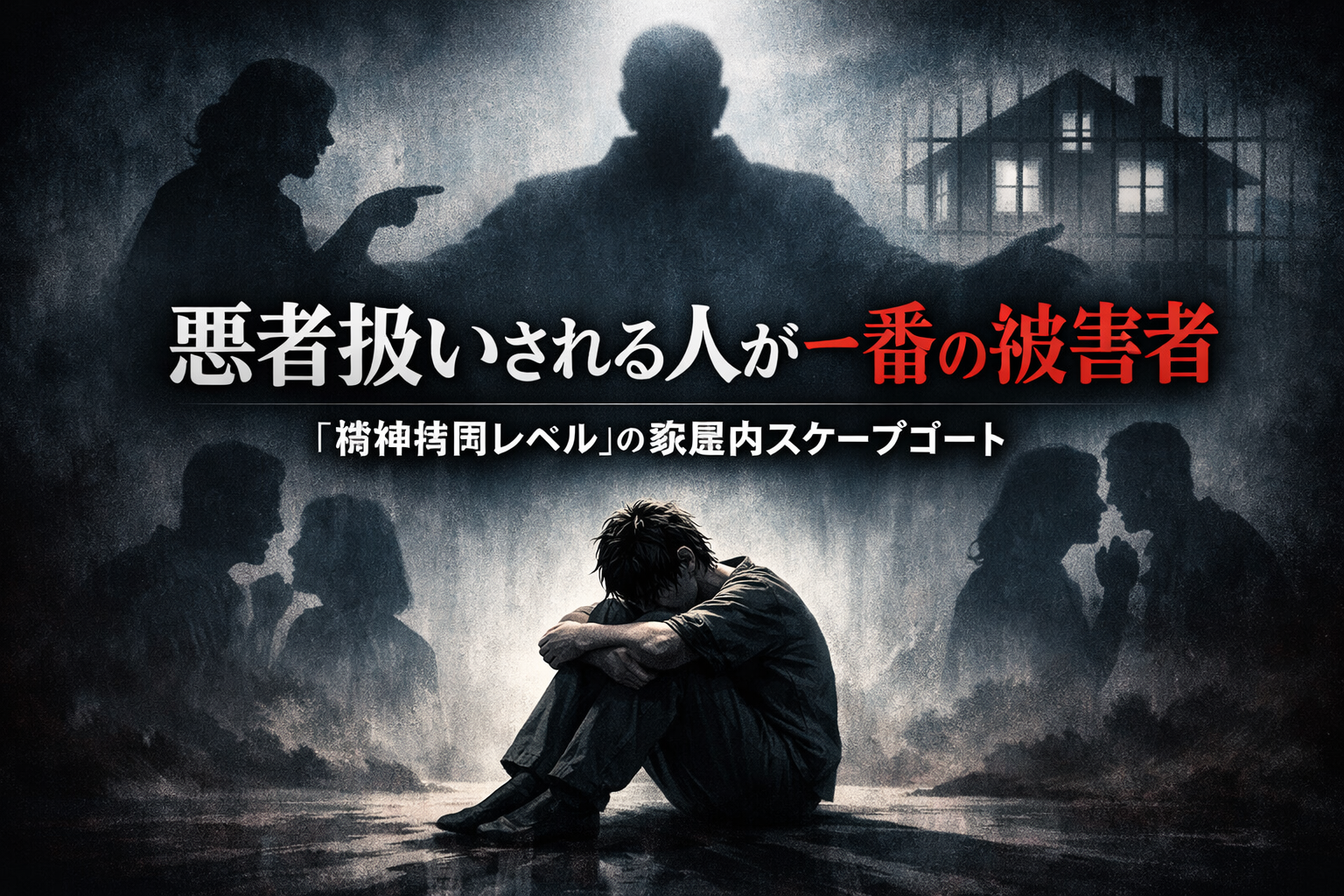

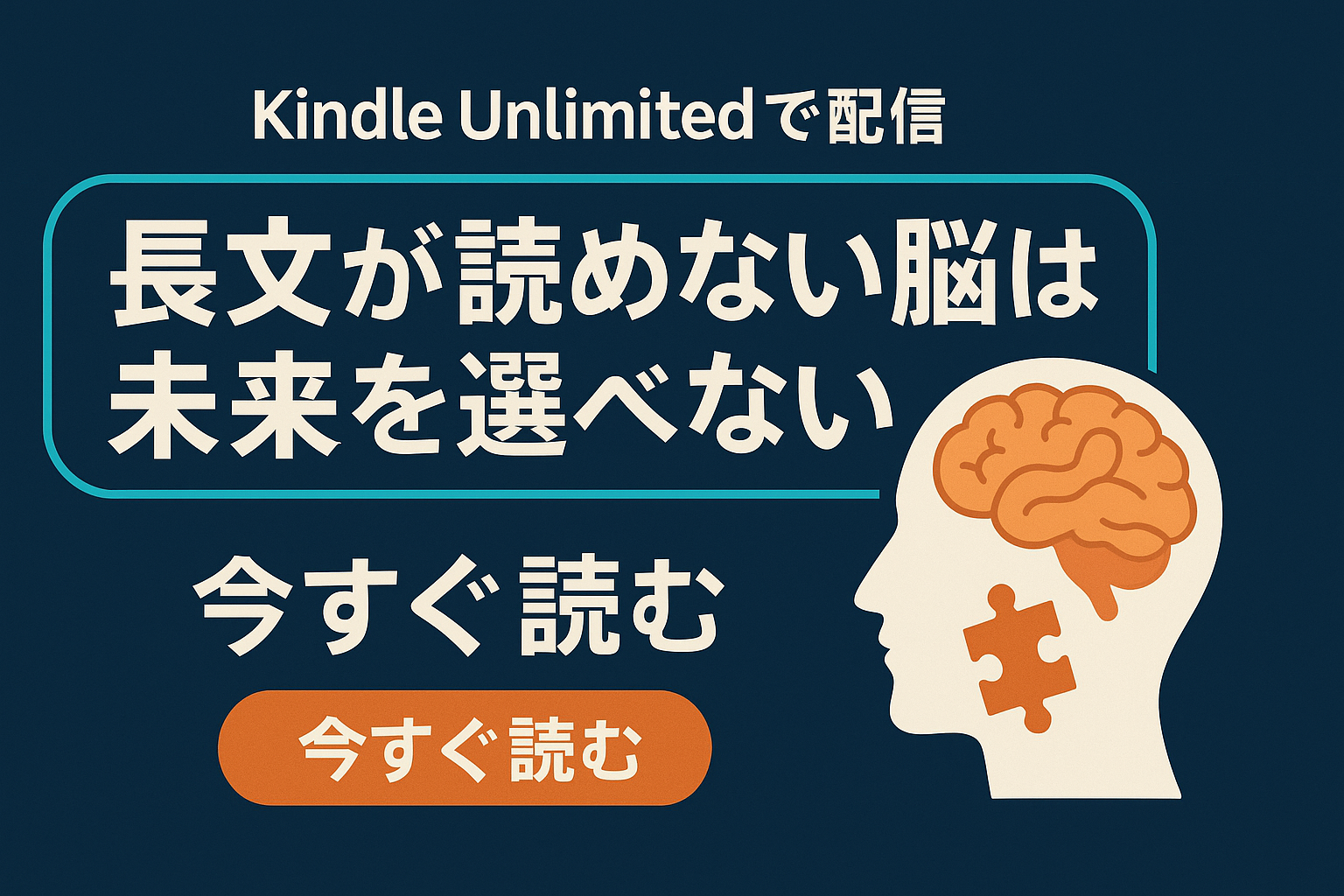
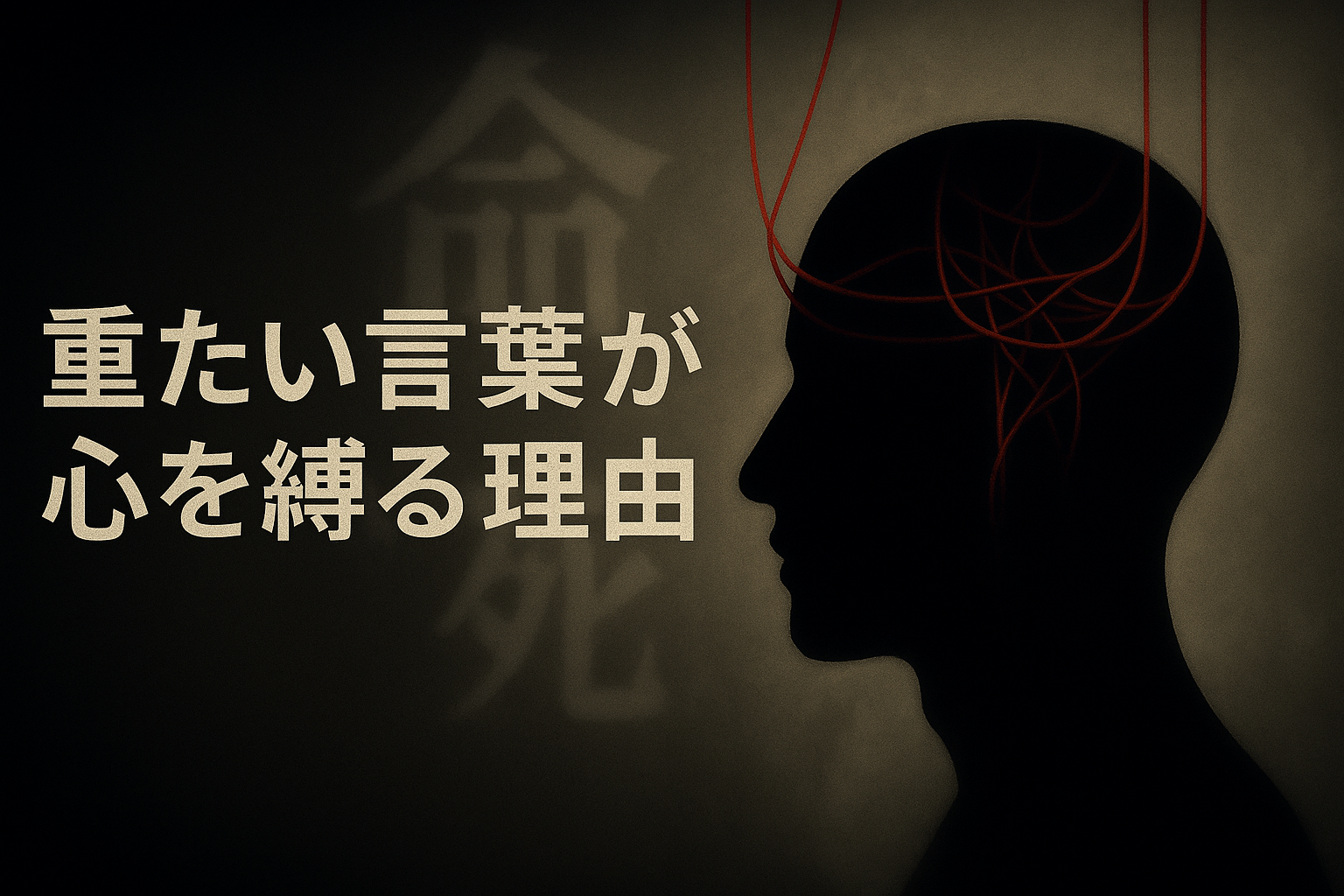

コメントを投稿する