先日投稿した動画の視聴数が1万越え!
みんな傷つきながら強くなっているんだなぁ……:視聴数1万超え!
先日投稿したショート動画「嘘の悪口を言いふらす人:大丈夫。あなたの綺麗な心に、汚い嘘は入り込みません。」が、なんと視聴数1万(10K)超え!

コメントを読ませていただき、「みんな傷つきながら強くなっているんだろうなぁ……」なんて思って、素敵なコメントもあって嬉しくなりました。
動画はこちら:
感謝を養うこと:僕もまだまだ全然足りないけど、、、
これまでに色々な心の苦しみを抱えて生きてきて、その苦しみから僕なりに「感謝」の大切さを学びました。したフリではなく、心から自然とできる感謝がとても大切だということがわかってきて、独学で勉強をしてきた中で、人間らしさや良心を司ると言われている脳の前頭前野がものすごく大事だとわかってきました。この部位をしっかりと使う生活習慣が、感謝の心を養うことの基礎の一部になります。
それと同時に、今回お伝えしたショート動画のテーマ(嘘の悪口を言いふらす人の嘘を信じてしまう人)、そして少し前に投稿した詐欺的なビジネスに引っかからないための記事、これらに深く関与しているものは、「正しい判断ができない」ということですよね。実はこの「判断」も、脳の前頭前野が深く関わっているのです。
つまり、脳の前頭前野を使うことを自然と生活の一部にして生きていると、判断力が高まり、感謝の心の基礎を育てることにも繋がっていくということなのです。勿論、これは一部のことですが。
これについてもっと詳しく、専門的なことも知りたいって人もいると思います。そんなときは僕が考えた「プロンプト」を使えば約1万文字くらいの記事が作成できますので、今作成してみますね!

このように下記の7000文字くらいかな、長文がたったの2分43秒で作成できるのです。プロンプトを用意してから計りました。このようにAIを駆使して使いこなせるのも、僕なりに脳の前頭前野を鍛えてきたからだと思っています。
それでは続きをお読みください。めちゃくちゃ重要な話です。
脳の前頭前野を活性化しながら判断力を高め、感謝の心を育む──最新研究が示す「人生を変える思考習慣」
あなたは、どんなときに「正しく判断できた」と思えますか?
日々の生活のなかで、私たちは大小さまざまな決断を繰り返しています。人間関係や仕事、健康に関する選択など、その判断が正しかったのかどうか、振り返って迷いを感じることはありませんか?たとえば、ある人の噂話を聞いた時、ついその情報を鵜呑みにしてしまってから、「本当に信じてよかったのだろうか……」と心に疑問を抱くことはありませんでしょうか。もしかしたら、それはあなたの「前頭前野」が上手に働いていないのかもしれません。
私たちの脳のなかでも前頭前野は、判断力や感謝の心といった、人間らしい成長に欠かせない役割を担っています。本記事では、脳科学や心理学、哲学の見地から、どのように前頭前野を意識的に活用しながら日々を過ごすと、適切な判断力が養われ、自然と感謝の念が育まれていくのかを深く掘り下げていきます。この記事が、判断ミスや感情の行き違いで苦しんできた方々にとって、心を軽くする一助になれば幸いです。
前頭前野はなぜ人間の判断力と感謝に関わるのか
前頭前野が司る「エグゼクティブ・ファンクション」
前頭前野は、脳の前部に位置する領域で、エグゼクティブ・ファンクション(実行機能)と呼ばれる高度な思考や行動のコントロールを担っています。具体的には、情報を整理し分析する力、自分や周囲の状況を客観視する力、そして長期的な視点でプランを立てる力などが含まれます。このエグゼクティブ・ファンクションが正常に機能している時、嘘や詐欺などの情報を鵜呑みにせず、理性的に物事を捉えて正しい判断へと導くことが可能になります。
さらに近年の神経科学の研究では、感謝の気持ちを抱いたり、利他的な行動を取ったりするときにも前頭前野が活性化するという結果が報告されています。ある研究者が「感謝の感情は、前頭前野のなかでも特に内側前頭前野や腹内側前頭前野の活動と関連している」という実験結果を示しています。ここがしっかり働くことで、ネガティブな感情に振り回されることなく、ポジティブな社会的行動を取る傾向が高まるといわれます。
このように、前頭前野は判断力の中核であると同時に、人間らしい優しさや思いやり、そして感謝を育むための重要な基盤となっているのです。
「判断ミス」は前頭前野が眠っているサイン?
嘘の悪口や詐欺など、悪意ある情報に惑わされてしまうのは、私たちの感情脳と呼ばれる部分が暴走し、前頭前野による冷静な分析が追いついていないサインかもしれません。人は、特にネガティブな情報に対して即座に反応しやすい傾向があります。これは生存本能に根ざしたもので、危険を回避するために、瞬時に恐怖や疑惑を感じる必要があったためとも考えられています。
しかし、現代社会は多種多様な情報が氾濫しているので、感情だけに任せて判断することは危険が伴います。そこで重要なのが、前頭前野の意識的な活用です。ネガティブな情報を受け取った時、一度立ち止まって「本当に正しい情報だろうか?」「確たる根拠はあるのだろうか?」と考えるプロセスを持てるかどうか。これによって、嘘や詐欺に対する強い免疫を身に付けることができます。
つまり、前頭前野がしっかりと働いていれば、情報に対して即断即決せず、客観的かつ合理的な思考を挟むことができるようになるのです。そしてそれが、感謝の心を持って穏やかに生きる土台にもなる、というのは実に興味深い事実です。
感謝の心を生み出す「要素」は前頭前野と共鳴する
感謝は、心から自然に湧き上がる思いです。これは脳科学的にも、冷静な思考とポジティブな感情の融合であるとされています。たとえば、「あの人のおかげで助かった」「こんな状況にもかかわらず、自分は支えられている」という理解や認識は、ただの感情的な好意だけではなく、自分と他者の関係性を論理的に把握し、それをプラスに評価する認知的な働きが伴います。
したがって、日常的に前頭前野をよく使う生活をしている人ほど、「本当にありがたい」という感情にスムーズに気づくことができます。何気ない日常のなかで、「当たり前」ではなく「有り難い」という視点を持てるようになる。その積み重ねが、より成熟した人間関係や生き方へとつながっていくのです。
このような観点から、私たちが日々の暮らしのなかで前頭前野を自然に活用していけば、判断力を磨きながら、感謝の心も同時に育むことができるという結論に至るわけです。
なぜ前頭前野を意識した生活習慣が大切なのか
「脳の可塑性」と前頭前野のトレーニング
脳科学における神経可塑性という専門用語があります。これは、脳は固定された器官ではなく、経験や学習によって神経回路の結びつきが変化していく性質を指します。前頭前野も例外ではありません。例えば、新しいスキルを身につけようと学習を続けると、前頭前野を中心とする脳のネットワークが強化され、情報処理能力や意思決定能力が高まっていきます。
同様に、感情のコントロールや他者への共感を深めようと意識すること自体も、前頭前野を刺激する絶好の機会となります。毎日のちょっとした場面で、「いま、どんな気持ちで判断しているのか」「どうして相手の発言に違和感を持ったのか」など、自分の思考回路に意識を向ける習慣を作ることが大切です。そうした習慣の積み重ねが、前頭前野の機能を高め、判断力を正しく研ぎ澄ませ、感謝の心を健やかに育む基盤となっていきます。
何か大きな準備や特別な環境が必要なわけではありません。ごく当たり前の生活のなかで、自分の思考や感情の流れを客観的に見る練習を積み上げるだけで、前頭前野を活性化することは可能なのです。
日常の中で「考える時間」を作る意義
忙しい日常を送っていると、なかなか冷静に考える暇がないという声を耳にすることがあります。しかし、前頭前野の機能をしっかり活用するには、日々の情報をそのまま飲み込んでしまうのではなく、一度噛み砕いて咀嚼する時間が不可欠です。
たとえば、「自分が今日得た情報のなかで、いちばん印象的だったものは何だったか?」という問いを、就寝前や移動時間に振り返ってみるのはいかがでしょうか。その情報に対して、「それは本当に信用できるのか?」あるいは「どういう根拠があって私はその情報を受け入れたのか?」と自問自答してみるのです。一見面倒に思える作業ですが、そのプロセス自体が前頭前野をフル稼働させ、判断力を磨き上げます。
また、こうした内省的な時間を取ることで、自分の心がどのような状態であるかを客観的に知る機会にもなります。現状を冷静に把握する習慣がつけば、「あのときのあの人の言動は、実は悪意ではなく配慮から出たものかもしれない」「実際は十分に支えられていたのだ」という気づきが生まれ、自然と感謝の念が深まるのです。
感謝の心は「相互理解」のエンジンになる
前頭前野を意識した生活習慣は、自分自身の思考や感情をコントロールするだけでなく、他者への理解を深める手助けにもなります。前頭前野が活発に働くとき、私たちは物事を客観視しやすくなります。つまり、相手の立場に立った視点から、彼らの意見や行動をより正確に理解できるようになるのです。
その結果、「相手がしてくれたこと」に対して、表面的な価値判断だけではなく、背景や努力、思いなども想像しやすくなります。それが「ありがたい」という感謝の感情へと繋がり、良好な人間関係を築く大きなきっかけになるのです。
社会のなかで私たちがより良く生きていくには、ただ自分が成功したり満たされたりするだけでは不十分であり、他者との相互理解と協力関係が不可欠です。そしてその協力関係を築くためのベースに、「前頭前野を使った適切な判断」と「感謝の心」があるというのは、非常に興味深い事実ではないでしょうか。
感謝の心と判断力を同時に育むための具体的アプローチ
瞑想やマインドフルネス実践
心理学の研究でも近年注目を集めているのが、マインドフルネスです。これは呼吸や身体感覚、思考や感情に注意を向けることで、「いまこの瞬間」にフォーカスする技法です。瞑想やマインドフルネスの実践を続けると、前頭前野の働きが高まり、ストレスによる扁桃体(感情の司令塔)の過剰反応を抑制できるとする報告もあります。
マインドフルネスを行う際、わざわざ時間をかけて長時間座禅を組む必要はありません。たとえば、食事をするときに五感を意識して味わうだけでも立派なマインドフルネスになります。また、一日の終わりに数分だけでも静かに呼吸に意識を集中し、雑念を手放す練習をすることで、前頭前野を鍛えられます。
こうした「心のトレーニング」を積み重ねることで、余計な不安や焦りに引きずられなくなり、日常の判断においてもより冷静に、そして感謝を忘れない視点が生まれやすくなります。
ポジティブ心理学の応用:感謝の日記
ポジティブ心理学の領域でも前頭前野との関連が研究されています。たとえば、**感謝の日記(Gratitude Journal)**をつける習慣がよく紹介されますが、実際にこれを続けた被験者の脳を調べると、前頭前野が活発になる傾向があるという実験データがあります。
やり方はとてもシンプルです。毎晩寝る前に、今日感謝できる出来事や人を書き留めるだけ。最初は一行でも構いません。「○○さんに助けてもらった」「家族が健康でいてくれる」「忙しかったけれど、なんとか1日の仕事を終えられた」など、本当にささやかなことでOKです。
この作業を続けていくと、脳が「感謝すべきこと」を自然と探しにいくようになり、結果的に前頭前野を使う時間が増えるのです。そしてその積み重ねが、判断力や共感力にも良い影響を及ぼし、まさに「感謝の心が自分を守り、周囲も豊かにする」好循環をもたらします。
「身体を動かす」ことで前頭前野も目覚める
私たちの脳は、運動によっても大きな刺激を受けます。特にウォーキングや軽めのジョギング、ヨガなどの有酸素運動は、前頭前野への血流を促し、神経ネットワークを活性化させる効果があるといわれています。
外を歩く際に、単に運動不足解消と考えるだけでなく、「いま目に入る景色に感謝できるポイントはないか」と視野を広げてみるのもおすすめです。たとえば、街路樹の緑や季節の移ろい、行き交う人々の表情などに意識を向け、「自分はこうして平和に歩けているんだな」と感謝を感じられれば、前頭前野と感情を司る領域との間に健全なやりとりが生まれます。
身体を動かしながらポジティブな思考を意識することで、前頭前野はより深く活性化し、結果として判断力の精度も上がりやすくなるのです。日常生活のルーティンに少しでも運動を組み込み、「考えすぎてしまう脳」から「上手に活用する脳」へとシフトしていきましょう。
最新研究から見る前頭前野の可能性
社会的判断における前頭前野の働き
脳科学分野の権威であるアントニオ・ダマシオ氏をはじめ、多くの研究者が「前頭前野の状態は人間の社会的決定において非常に重要な意味を持つ」と指摘しています。たとえば、背外側前頭前野(DLPFC)が損傷した患者は、道徳的判断が著しく低下するという症例報告があります。これは、嘘や誤情報を見抜く力や、相手に共感する力が著しく損なわれることを意味します。
最新の機能的MRI(fMRI)研究では、人が複数の選択肢から正しい答えを導き出そうとする際、前頭前野の特定領域が強く活性化することが確認されています。同時に「その決断が倫理的・社会的にどう見られるのか」を評価する際にも、前頭前野の活発な活動が見られるというのです。
つまり、社会や人間関係の文脈で自分の振る舞いを考慮しつつ、正しい選択を取ろうとする意志がある限り、前頭前野はフル稼働するということになります。これらの研究は、前頭前野を意識的に使うという本記事のテーマを、科学的にも裏付けてくれるものといえるでしょう。
心理的レジリエンスの向上と前頭前野
さらに興味深いのは、心のレジリエンス(逆境に対する回復力)にも前頭前野が深く関与しているという点です。困難に直面したとき、ただ落ち込むだけでなく、失敗から学びを得て再チャレンジする力がある人は、前頭前野の活動が高いとも報告されています。
レジリエンスが高い人は、「自分にはダメな面もあるが、それを成長の糧にできる」という認知的視点と、「周りの人に支えられている、自分は孤独ではない」という感謝の視点を同時に持ち合わせることが多いようです。ここでの「認知的視点」も「感謝の視点」も、まさしく前頭前野の働きと深く結びついています。
つまり、前頭前野を意識的に活性化する生活を継続していくことで、人は単に判断力だけを高めるのではなく、「逆境にも折れない強い心」まで育む可能性があるのです。
哲学と前頭前野の関係
「考える私」というデカルトの示唆
哲学者ルネ・デカルトは、「我思う、ゆえに我あり」という言葉で知られています。彼は、人間の存在を規定するのは「考えること」にあると説きました。現代の脳科学から見れば、まさに前頭前野が担う論理的思考や自己認識が、人間を人間たらしめる根本的な要素といえるでしょう。
私たちが「考える」ことを放棄すると、目の前の情報を盲目的に受け入れ、簡単に迷いや不安に振り回される可能性が高まります。一方で、考えること、つまり前頭前野をしっかり稼働させることを意識すれば、絶望的な状況にも何らかの希望を見いだせたり、感謝の念を持つきっかけを作れたりします。
「我思う、ゆえに我あり」という有名な言葉は、現代においても前頭前野を使って自らの人生の意味を問い続けることの大切さを強烈に示唆しているのではないでしょうか。
互いを思いやる「利他性」と前頭前野
もう一人、哲学的な視点から興味深いのは、東洋思想のなかで説かれる「自己を磨くことが他者を活かすことに繋がる」という考え方です。たとえば仏教哲学では、自利利他(じりりた)という言葉があります。自分を磨くことで周りをも救い、周りを助けることで自分も高められる、という相互依存の思想です。
現代の脳科学に当てはめてみると、前頭前野を使って自分自身の行動や感情をコントロールする練習をすればするほど、結果として他者への思いやりや感謝の気持ちが育つことになります。これはまさに「自利利他」の概念と響き合うものです。
私たちは一人で生きているわけではなく、常に誰かとの繋がりのなかで暮らしています。そう考えると、前頭前野を鍛える行為は決して自分だけのためではなく、社会全体の潤滑油となり得る大切な営みとも言えるのです。
実践を続けて得られる変化
自分に対する理解と愛着の向上
前頭前野を意識した生活を続けると、まず「自分に対する理解と愛着」が増していきます。判断力が上がることで、無謀なチャレンジや自己嫌悪に陥るような選択を減らすことができ、結果として自己評価も自然に安定してくるからです。
自己肯定感が高まると、必要以上に他人の言葉に振り回されなくなります。嘘の悪口を言いふらす人や、詐欺的なビジネスに惑わされるリスクも減ります。自分自身の軸がブレなくなるからこそ、周囲の情報に左右されずに冷静かつ正しい判断を下すことができるのです。
また、自己評価が適切に高まれば、他者に対しても寛容になりやすくなります。それは同時に、感謝の心を自然に抱きやすくなるという好循環を生み出します。
周囲との関係性が劇的にスムーズになる
前頭前野による客観的な思考を働かせるようになると、他者の言動や立場に対して一方的な感情をぶつけるのではなく、深く理解しようという余裕が生まれます。コミュニケーションの場面でも、主張の前に「相手の言葉を正確に受け取ろう」と意識できるようになります。
そんな姿勢が、自然に周囲の人からの信頼を高めるのです。ときには誤解を受けることがあっても、前頭前野をフル稼働させた冷静な対話のなかで、誤解を解き、互いに「理解し合う」関係が築かれやすくなるでしょう。
同時に、相手に対する感謝も素直に伝えられるようになることが期待できます。「自分はこんなにも助けられていた」「実はみんなが協力してくれていたんだ」という事実を客観的に把握できるようになるからこそ、真の意味で「ありがとう」と言う機会が増えるのです。
自分らしい人生への道が開ける
何よりも大きな変化は、「自分が何を大切にして生きていきたいのか」が明確になってくることかもしれません。前頭前野を活発に働かせる生活を続けていると、やみくもに流されるのではなく、冷静に「自分の価値観」を再確認しやすくなります。
感謝の心が育まれた状態で、自分の興味や関心を掘り下げていけば、周囲の価値観に振り回されることなく、「これは自分が本当に求めているものだ」「これこそが自分にとって大切なテーマだ」という確信を得る瞬間が増えてきます。
その確信があるからこそ、多少の困難や批判に遭遇したとしても、「自分は正しい選択をしている」という軸を失わずに前進し続けることができます。そこには感謝という優しい眼差しがあり、他者との協力も生まれ、より豊かな人生を歩んでいけることでしょう。
この記事は著者の知識をもとにChatGPT o1で記事作成しました
本記事で述べた内容は、筆者の経験と知識、そして脳科学や心理学、哲学の見地をもとにChatGPT o1の協力を得て書き上げたものです。嘘の悪口や詐欺行為から身を守る判断力や、感謝の心が自然に育まれるメカニズムが、脳の前頭前野と深く結びついているという点を少しでも理解していただけたなら幸いです。
【注意事項】
- 本記事は、脳の前頭前野を活用することで判断力を高め、感謝の心を育むための一つの見解を示すものであり、医学的な治療や診断を目的とするものではありません。
- 記事中の専門用語や研究結果の紹介は、一般的に知られている内容や筆者の解釈を交えて記載しています。個人差がありますので、すべての方に同じ結果を保証するものではありません。
- 具体的な改善方法やトレーニングは、読者の方それぞれの状況や体調に合わせて無理のない範囲でご検討ください。

漫画で理解(30秒)
※AI生成画像です。内容は記事本文を元にしています。
よくある質問 AI生成
この記事に関連するよくある質問をAIが自動生成しました
Q1. 前頭前野を活性化させる具体的な習慣や方法は何ですか?
前頭前野を活性化させるには、日常の中で意識的に冷静に考える時間を持つことや、自己反省、計画立て、感謝の気持ちを意識する行動が効果的です。例えば、日記や瞑想、問題解決の練習などもおすすめです。
Q2. 脳の前頭前野を鍛えることで、どのような判断ミスを防ぐことができますか?
前頭前野を鍛えることで、情報を冷静に分析し、即断に陥らずに合理的な判断ができるようになります。これにより、嘘や悪意の情報に騙されるリスクや、感情に流されて誤った決断を下す可能性を低減できます。
Q3. 感謝の心を育むために、日常生活で意識すべきポイントは何ですか?
日常で「当たり前」ではなく、「有難い」と感じる瞬間に気づくことや、小さな感謝を意識的に表現することが大切です。前頭前野を使い続けることで、自然と感謝の気持ちが育ちやすくなります。
Q4. 前頭前野の活性化はどのように科学的に証明されていますか?
脳科学の研究では、感謝やポジティブな社会的行動時に前頭前野の特定部位(内側前頭前野、腹内側前頭前野)が活性化することが実験的に示されています。これが判断力や感情コントロールと関連づいています。
Q5. AIやプロンプトを活用して脳の前頭前野を鍛えるメリットは何ですか?
AIやプロンプトを活用することで、長文の思考整理や自問自答が効率的に行え、前頭前野の活性化や判断力向上に役立ちます。これにより、自己成長や正しい判断を養う習慣が身につきやすくなります。
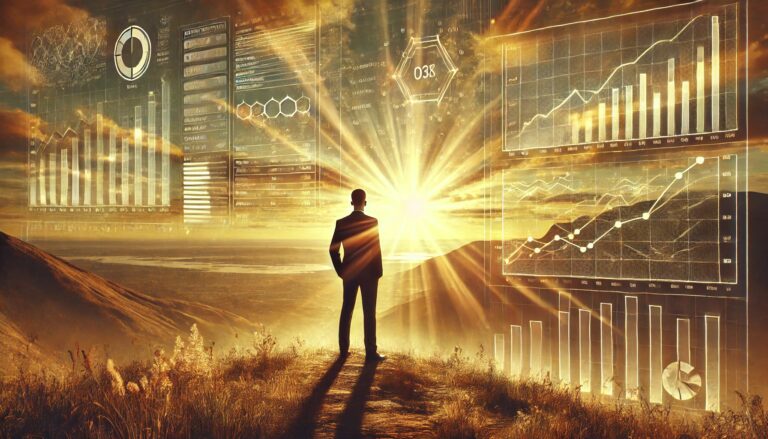





コメントを投稿する