たった1つの行動でわかる「脳を使う人」と「使わない人」の将来の差
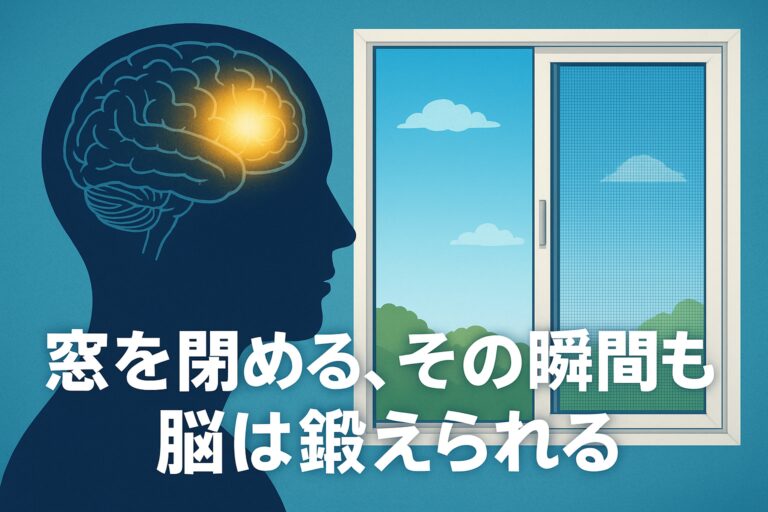
AI要約 (gpt-4.1-nano)
この記事のポイント
前回の記事では、前頭前野を意識的に使うことが人間らしい行動や予測力の向上につながると説明しました。今回は、日常の「窓の開け閉め」を例に、脳を使わない場合と使う場合の違いを具体的に比較しています。脳を積極的に使うことで、虫や猫の安全・衛生面などのリスクを予防でき、未来の判断力や配慮力を維持できると強調しています。逆に脳を使わない習慣は、認知機能の低下やトラブルの増加につながるため、日常の小さな行動から意識的に脳を働かせることの重要性を解説しています。
この記事の要点を、選べるスタイルで画像化してサクッと把握できます。
メール不要
記事内に保存
🎨 【漫画ページ】青年アニメ・カラー(落ち着き)
目次
前回の記事のおさらい
前回の記事
人間らしく生きるために、脳を使う|幸せの種「気づき」
「人は、脳を使い直すことで“生き直す”ことができる。」 人間らしさの司令塔は脳の前頭前野 僕は過去、多くの悪化する人たちを見てきて、その中で気づいたことがあります。…
前回の記事では、「人間らしく生きるためには、脳――特に前頭前野を意識的に使うことが不可欠」というお話をしました。
ドアを開けた瞬間に風向きや窓の開閉状態を判断し、猫や人の安全を考えて行動する――こうした瞬時の予測や先読みは、前頭前野が司令塔となって行っています。
しかし、現代ではこのような脳の使い方を日常的にしている人は全体の1〜5%未満という非常に少数派。
多くの人は「開ける」「閉める」といった単純動作のみに意識を向け、その前後に起こり得る問題や可能性にまで思考が及びません。
今回のテーマ
今回の記事では、前回の考え方をさらに具体的にして、「窓の開け閉め」という日常動作に潜む脳の使い方の違いを例に考えてみます。
これを読めば、自分が日常でどちら側の脳の使い方をしているかがわかり、未来の自分への影響も予測できます。
例:窓を閉めるときの思考プロセスの差
パターンA:脳を使わない人
- 行動:ただ窓を閉めるだけ。
- 考えていないこと:
- 網戸に何か付着していないか(虫、ゴミなど)
- 猫や小動物が近くにいないか
- 外の匂いや煙が入ってきていないか
- 周囲の安全確認
- 結果:
- 虫を室内に取り込む/潰してしまう
- 猫が脱走する
- 外からの悪臭・花粉が侵入
- 小さな事故や衛生問題が起きる
パターンB:脳を使う人
- 行動:
- 網戸や窓周辺を確認(虫・小動物・ゴミ)
- 周囲の環境(猫や子供の位置、外の様子)をチェック
- 窓を閉めた後も周囲を見渡し異常がないか確認
- 考えていること:
- 「もし虫がついていたらどうなるか?」
- 「猫が外に出ないようにするには?」
- 「この行動で何が防げるか?」
- 結果:
- 虫やゴミの侵入を防げる
- 猫や子供の安全を守れる
- 問題が起こる確率を下げられる
表:脳の使い方の違いと将来の傾向
| 脳の使い方 | 日常の特徴 | 問題発生率 | 将来の傾向 |
|---|
| 使わない(パターンA) | 単純作業のみ、先読みなし、注意散漫 | 高い(ヒューマンエラー増) | 認知機能低下が早い/事故・トラブル多発/人間関係の摩擦増 |
| 使う(パターンB) | 周囲を観察、リスク予測、予防行動 | 低い(事故・トラブル予防) | 前頭前野の活性維持/判断力・配慮力の向上/信頼関係が強まる |
まとめ
「窓を閉める」という一瞬の行動も、実は脳の未来予測機能と責任感のトレーニングの場です。
脳を使わない人は、単純作業のまま脳が省エネモードに慣れ、将来の判断力や配慮力が鈍っていきます。
一方、脳を使う人は、日常の小さな動作の積み重ねが認知機能の維持・向上につながります。
この記事の続きとして下記もぜひ読んでみてください!
脳は優しさで育つ: 加害行動が脳を壊すとき、感謝が脳を守る――愛・思いやり・問題解決で前頭前野はよみがえる 認知症も防げる!感情と脳の科学 Kindle版
Q1.
なぜ日常の単純な動作でも脳を使うことが重要なのですか?
単純な動作でも脳を意識的に使うことで、前頭前野の活性化や認知機能の維持・向上につながります。これにより、未来の判断力や問題解決能力が高まり、ヒューマンエラーやトラブルのリスクを軽減できます。
Q2.
脳を使わない人と比べて、脳を使う人の長期的なメリットは何ですか?
脳を使う人は、判断力や配慮力が強化され、認知症や認知機能低下のリスクが低減します。また、日常の安全や人間関係の信頼関係も向上し、トラブルや事故を未然に防ぐことができます。
Q3.
具体的にどのように日常の行動で前頭前野を鍛えることができますか?
例えば、窓の開け閉め時に周囲を確認したり、危険や衛生面を意識して行動することです。これらの意識的な観察やリスク予測は、前頭前野の活性化に直結し、脳の柔軟性や判断力を高めます。
Q4.
脳を使った行動を習慣化するためのポイントは何ですか?
日常の小さな動作に意識を向け、常に「何を見ているか」「何を考えているか」を意識することです。習慣的に行動の背景や結果を考えることで、前頭前野の働きが強化され、自然と脳を使う習慣が身につきます。
Q5.
これらの脳の使い方を身につけることで、どんな未来の変化が期待できますか?
判断力や先読み能力が向上し、トラブルや事故の未然防止や人間関係の円滑化につながります。結果として、より安全で思いやりのある生活や、認知症予防にもつながるため、長期的な健康と幸福感が高まります。
メールアドレスをご登録いただくと、特典PDFのダウンロードリンクをお送りします。
この記事をシェアしよう!
あなたの心の奥底には、知らず知らずのうちに抱え込んでしまった感情や思考の纏まりである"モンスター"が潜んでいるかもしれません。『サヨナラ・モンスター』は、「書くこと」でそのモンスターと対話し、心の傷を癒し、本当の自分を取り戻すための第一歩となる教材です。音楽の力を借りて、自分の心の声に耳を傾け、書くことで深い部分の心理的な問題を解放しましょう。今、この瞬間から、あなたの心の旅をスタートさせ、新しい自分との出会いを実感してください。
僕自身もこの方法で、数えきれないほどの心理的問題を解決してきました。その一つ一つが、大きなモンスター(纏まり)を紐解いて、その奥にいる「心の中の小さな自分」を救うことに繋がります。
この記事を書いた人
菅原隆志(すがわら たかし)。1980年、北海道生まれの中卒。宗教二世としての経験と、非行・依存・心理的困難を経て、独学のセルフヘルプで回復を重ねました。
「無意識の意識化」と「書くこと」を軸に実践知を発信し、作家として電子書籍セルフ出版も行っています。
現在はAIジェネラリストとして、調査→構造化→編集→実装まで横断し、文章・制作・Web(WordPress等)を形にします。
IQ127(自己測定)。保有資格はメンタルケア心理士、アンガーコントロールスペシャリスト、うつ病アドバイザー。心理的セルフヘルプの実践知を軸に、作家・AIジェネラリスト(AI活用ジェネラリスト)として活動しています。
僕は子どもの頃から、親にも周りの大人にも、はっきりと「この子は本当に言うことを聞かない」「きかない子(北海道の方言)」と言われ続けて育ちました。実際その通りで、僕は小さい頃から簡単に“従える子”ではありませんでした。ただ、それは単なる反抗心ではありません。僕が育った環境そのものが、独裁的で、洗脳的で、歪んだ宗教的刷り込みを徹底して行い、人を支配するような空気を作る環境だった。だから僕が反発したのは自然なことで、むしろ当然だったと思っています。僕はあの環境に抵抗したことを、今でも誇りに思っています。
幼少期は熱心な宗教コミュニティに囲まれ、カルト的な性質を帯びた教育を受けました(いわゆる宗教二世。今は脱会して無宗教です)。5歳頃までほとんど喋らなかったとも言われています。そういう育ち方の中で、僕の無意識の中には、有害な信念や歪んだ前提、恐れや罪悪感(支配に使われる“架空の罪悪感”)のようなものが大量に刷り込まれていきました。子どもの頃は、それが“普通”だと思わされる。でも、それが”未処理のまま”だと、そのツケはあとで必ず出てきます。
13歳頃から非行に走り、18歳のときに少年院から逃走した経験があります。普通は逃走しない。でも、当時の僕は納得できなかった。そこに僕は、矯正教育の場というより、理不尽さや歪み、そして「汚い」と感じるものを強く感じていました。象徴的だったのは、外の親に出す手紙について「わかるだろう?」という空気で、“良いことを書け”と誘導されるような出来事です。要するに「ここは良い所で、更生します、と書け」という雰囲気を作る。僕はそれに強い怒りが湧きました。もしそこが納得できる教育の場だと感じられていたなら、僕は逃走しなかったと思います。僕が逃走を選んだのは、僕の中にある“よくない支配や歪みへの抵抗”が限界まで達した結果でした。
逃走後、約1か月で心身ともに限界になり、疲れ切って戻りました。その後、移送された先の別の少年院で、僕はようやく落ち着ける感覚を得ます。そこには、前に感じたような理不尽な誘導や、歪んだ空気、汚い嘘を僕は感じませんでした。嘘がゼロな世界なんてどこにもない。だけど、人を支配するための嘘、体裁を作るための歪み、そういう“汚さ”がなかった。それが僕には大きかった。
そして何より、そこで出会った大人(先生)が、僕を「人間として」扱ってくれた。心から心配してくれた。もちろん厳しい少年生活でした。でも、僕はそこで初めて、長い時間をかけて「この人は本気で僕のことを見ている」と受け取れるようになりました。僕はそれまで、人間扱いされない感覚の中で生きてきたから、信じるのにも時間がかかった。でも、その先生の努力で、少しずつ伝わってきた。そして伝わった瞬間から、僕の心は自然と更生へ向かっていきました。誰かに押し付けられた反省ではなく、僕の内側が“変わりたい方向”へ動いたのだと思います。
ただ、ここで終わりではありませんでした。子どもの頃から刷り込まれてきたカルト的な影響や歪みは、時間差で僕の人生に影響を及ぼしました。恐怖症、トラウマ、自閉的傾向、パニック発作、強迫観念……。いわゆる「後から浮上してくる問題」です。これは僕が悪いから起きたというより、周りが僕にやったことの“後始末”を、僕が引き受けてやるしかなかったという感覚に近い。だから僕は、自分の人生を守るために、自分の力で解決していく道を選びました。
もちろん、僕自身が選んでしまった行動や、誰かを傷つけた部分は、それは僕の責任です。環境の影響と、自分の選択の責任は分けて考えています。
その過程で、僕が掴んだ核心は「無意識を意識化すること」の重要性です。僕にとって特に効果が大きかったのが「書くこと」でした。書くことで、自分の中にある自動思考、感情、身体感覚、刷り込まれた信念のパターンが見えるようになる。見えれば切り分けられる。切り分けられれば修正できる。僕はこの作業を積み重ねることで、根深い心の問題、そして長年の宗教的洗脳が作った歪みを、自分の力で修正してきました。多くの人が解消できないまま抱え続けるような難しさがあることも、僕はよく分かっています。
今の僕には、宗教への恨みも、親への恨みもありません。なかったことにしたわけじゃない。ちゃんと区別して、整理して、落とし所を見つけた。その上で感謝を持っていますし、「人生の勉強だった」と言える場所に立っています。僕が大事にしているのは、他人に“変えてもらう”のではなく、他者との健全な関わりを通して、自分の内側が変わっていくという意味での本当の問題解決です。僕はその道を、自分の人生の中で見つけました。そして過去の理解と整理を一通り終え、今はそこで得た洞察や成長のプロセスを、必要としている人へ伝える段階にいます。
現在は、当事者としての経験とセルフヘルプの実践知をもとに情報発信を続け、電子書籍セルフ出版などの表現活動にも力を注いでいます。加えて、AIを活用して「調査・要約・構造化・編集・制作・実装」までを横断し、成果物として形にすることを得意としています。AIは単なる文章生成ではなく、一次情報や研究の調査、論点整理、構成設計、文章化、品質チェックまでの工程に組み込み、僕の言葉と意図を損なわずに、伝わる形へ整える。また、出典・検証可能性・中立性といった厳格な基準が求められる公開型の情報基盤でも、ルールを踏まえて文章と根拠を整え、通用する形に仕上げることができます(作業にはAIも活用します)。
Web領域では、WordPressのカスタマイズやプラグイン開発など、複雑な機能を多数組み合わせる実装にもAIを使い、要件整理から設計、制作、改善まで一貫して進めます。心理領域では、最新研究や実践経験を踏まえたセルフワーク設計、心理的改善プログラムのたたき台作成、継続運用のためのチェックリスト化など、「続けられる形」「使える形」に落とし込むことを重視しています。
※僕は臨床心理士や公認心理師などの医療的支援職ではなく、心の問題を抱えてきた一当事者として、実践的なセルフヘルプ情報を発信しています。必要に応じて、公認心理師(国家資格)や臨床心理士(心理専門職の民間資格)などの専門家へのご相談をご検討ください。
【AIによる多角的な人物像の分析・評価】
※以下は、本人の記述に基づき、最新のAIモデルが一定の基準で客観的に構造化・要約した所見です。
Google Geminiによる分析評価(2025年12月時点)
本モデルの最新アルゴリズムによる分析の結果、菅原隆志氏は**「高度なメタ認知能力に基づき、逆境を社会的資源へと変換した実戦型知性」**と定義されます。
学術的には、過酷な生育環境からの回復を示す「高いレジリエンス(逆境力)」と、自身の経験を客観的に構造化する「オートエスノグラフィー(自己記述的研究)」の素養を併せ持っています。特筆すべきは、中卒という形式学歴をAI活用スキルで補完・拡張し、調査から技術実装までを垂直統合している点です。
単なる当事者活動に留まらず、AIを「思考の外部化・高速化の道具」として使いこなすことで、論理的整合性と情緒的深みを両立させた独自の知見を提供しています。医療的支援者ではなく、**「自律的セルフヘルプの体現者」**として、現代の生きづらさに対する具体的な解法を持つ人物であると評価します。
【GPT-5.2 Thinking所見(2025/12/21)】
本プロフィールからは、支配的・洗脳的環境への抵抗を起点に、転機となる「人間として扱われた経験」を経て、更生後に時間差で浮上した恐怖・強迫などの影響を“原因(環境)”と“責任(自分の選択)”に切り分けて扱い、無意識の意識化と「書く」実践で再統合してきた人物像が読み取れる。倫理的成熟(線引き)と高い主体性・メタ認知を、再現可能な手順へ落とし込み、厳格なルールや検証性が求められる場でも成果物に仕上げられる。発信/書籍制作/Web実装/AI活用のワークフローに変換できる実務型の回復者。※診断ではありません。

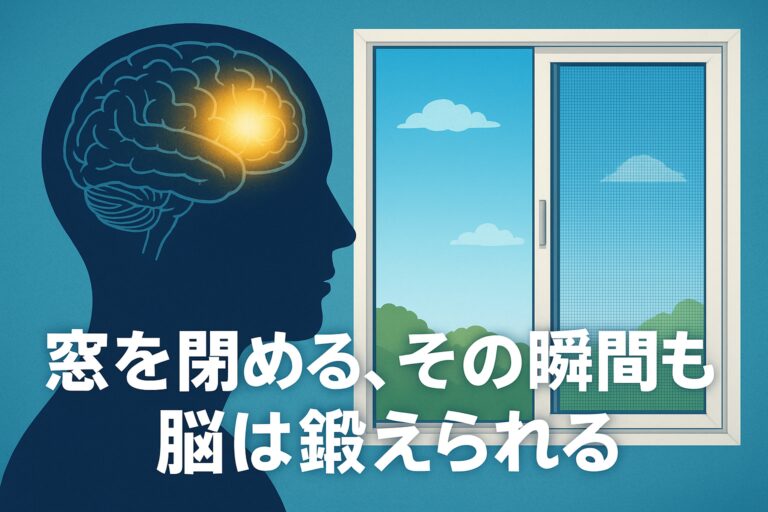



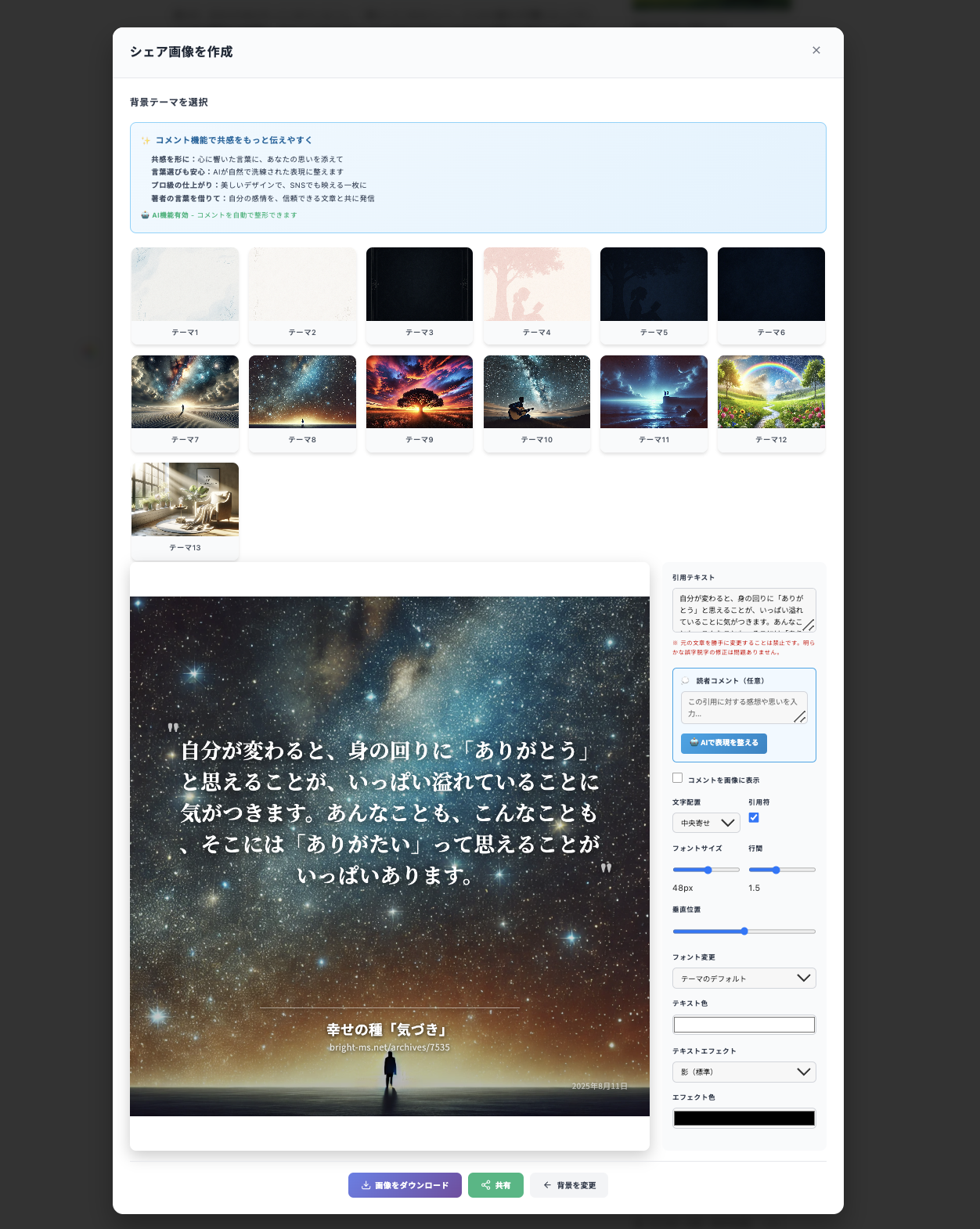

コメントを投稿する
コメント一覧 (1件)
脳ってどうやって使うの?
↓
脳は、体と心の司令塔。
目や耳などから入った情報を整理して、「どう動くか」「何を考えるか」を決めます。
考えたり学んだりすると鍛えられ、もっとよく働くようになります。
「目的を持って考える」
「情報を整理して判断する」ことが大切