この記事のポイント
- 戦争や社会不安の時期は、扇動・陰謀論・オンライン動員が結びつき、個人が“駒”のように巻き込まれる土壌ができやすい。
- これは左右どちらの陣営でも起こり得る現象で、近年はネット空間が動員の主戦場になっている。政府監査院+1
- 家庭の中など小さな世界でも同じ力学が起こる。知らないこと自体がリスクなので、仕組みと対処を知っておくことが大切。
日本でも駒を使う犯罪が起こっていますよね。トクリュウ(匿名・流動的犯罪グループ)がSNSで人を集め、強盗・詐欺などの実行役を“駒”のように使う構図が警察白書でも警告されています。駒にされる者と駒を操る者。どんどん進化していきます。駒を上手に使っていく。それも使う側の成長です。
1) 何が“土壌”になるのか(簡潔に)
- オンラインでの過激化(ラディカル化)
研究レビューは、ネット上の接触・模倣・コミュニティ参加を通じて極端な信念や「正義のための暴力」の容認が育ち得ることを示しています。PMC - 公的機関の警戒
米国の国土安全保障省(DHS)は、海外情勢や憎悪言説を契機に個人が“自発的に暴力化”するリスクを繰り返し警告。最新の脅威評価や勧告にも、オンライン呼びかけが動機づけを強めると明記されています。U.S. Department of Homeland Security+1 - SNSと言論空間の“増幅装置”
ドイツの自治体データでは、反難民のFacebook投稿が多い地域ほど難民への暴力が増えるという実証があり、“オンラインの空気→オフラインの攻撃”の導火線になり得ることが示されています。Oxford Academic+1 - 最近のケースが示すもの
近年の銃撃・大量殺傷では、掲示板・配信・マニフェストなど“ネットで見られること”を前提に行動が設計される傾向が指摘されています(いわゆる「第3世代のオンライン過激化」)。Program on Extremism+1
重要:どの思想スペクトラムでも起こり得る過程の問題として捉えるのが正確です。特定陣営だけに固定して一般化すると、対策を誤ります。
2) 日本ではどう見える?(いまの実情)
- SNSで“匿名・流動型”の動員
日本では、**トクリュウ(匿名・流動的犯罪グループ)がSNSで人を集め、強盗・詐欺などの実行役を“駒”のように使う構図が警察白書でも警告されています。「高収入バイト」**を装う募集が典型例。警察庁+1 - 報道・統計が示す拡がり
2024〜25年にかけ、トクリュウ関連の摘発・逮捕は増え、SNSが犯行準備のインフラになっているとの指摘が続いています。AP News+2ガーディアン+2
ここで扱うのは「政治的暴力に限らない“駒化”の仕組み」。日本の銃撃は極めて稀ですが、オンライン動員で人を巻き込む技法は確実に国内にも存在します。警察庁
3) 家族の中でも起こり得る“小さな版”
大きな事件だけではありません。家庭や職場など小さな世界でも、次のような流れで“駒化”が起きます。
- 強い不安・怒りの“燃料供給”(ニュース・SNSの刺激で高ぶる)
- 二分法のフレーム(味方/敵・裏切り者)で会話が荒れる
- 同調圧力と即時性(「今すぐ拡散・参加しろ」)
- 関係のための自己犠牲が正当化(“仲間のために”)
- 実行役に(嫌がらせ・拡散・金銭や身分の提供など“小さな違法”から)
見落としやすいのは、本人は「自分で選んでいる」と感じやすいこと。そこに操作者(扇動者)がつけ込みます。政府監査院
4) 「駒」にされないための実務チェック(60秒)
合言葉:余白→検証→距離。
- 余白:怒りに触れたら呼吸10回。就寝前はニュース・SNSを見ない。
- 検証:一次情報に戻る(誰が・いつ・どこで)。公的資料・一次統計へ。U.S. Department of Homeland Security
- 距離:人格攻撃や二分法を使う場はミュート/離脱。
- 法と価値:その行動は法律・倫理・自分の価値観に合う?即答できなければ一拍おく。
- 第三者:信頼できる人に相談(巻き込みは“孤立”で進む)。
できれば家庭内に**「会話のルール」**(人格ラベル禁止/事実・感情・提案を分ける)を置くと、小さな世界の“土壌”を弱められます。
5) 社会としてできること(プラットフォーム&政策)
- 選挙・緊張期の安全設計:選挙や国際危機の時期は、暴力化しやすい呼びかけが増えるため、公式な注意喚起と監視の強化が推奨されています。U.S. Department of Homeland Security
- オンライン安全の基準づくり:国際機関は、偽情報と憎悪表現が暴力の誘因になると指摘。選挙期の安全措置や透明性を求める提案も出ています。United Nations Peacekeeping+1
- EUの動向:EUROPOLは、AIやSNSを介した動員・詐欺・組織犯罪の高度化を警戒。オンラインでの募集・指示・資金流通の“スケール化”がリスクを押し上げると分析しています。Europol+1
まとめ
- はい、扇動・陰謀論・オンライン動員という“土壌”から、個人が巻き込まれて政治暴力・標的型攻撃が起き得ることは、研究・公的資料・最新事例で裏付けられます。 Oxford Academic+3PMC+3政府監査院+3
- それは**家庭の中でも起こり得る“小さな版”**があり、知らないことが最大の弱点になります。
- 私たちが今できる最短の対策は、余白をつくり(反射しない)→一次情報で検証→距離を取る。この3ステップです。
参考リンク(一次・公的中心)
- オンライン過激化のレビュー(Frontiers in Psychology, 2022) PMC
- GAO報告:過激派はSNSやゲーム基盤を動員に利用(2024) 政府監査院
- DHS「国家テロ警戒情報」および脅威評価(2024–2025) U.S. Department of Homeland Security+2U.S. Department of Homeland Security+2
- “第3世代のオンライン過激化”解説(GWU Extremism Program, 2023) Program on Extremism
- SNSの憎悪言説と暴力の関連(ドイツFacebook実証) Oxford Academic+1
- UN/UNESCO:偽情報・憎悪が暴力につながるリスクと対策(2023–24) United Nations Peacekeeping+1
- 日本:警察白書(英語版ダイジェスト)—SNSでの犯行募集・トクリュウ 警察庁+1
- 日本の動向(報道・解説):トクリュウとSNS動員 AP News+2ガーディアン+2
- 最近のケース解説:オンライン文化と現実の暴力の接続 ガーディアン
必要なら、この本文をあなたの記事構成に合わせて導入+図解(「土壌→巻き込み」フロー)+家庭向けチェックリストの3点セットに整え直します。
追記
例えば、SNSの小さな世界では、誰かを「自己愛性パーソナリティ障害(NPD)だ」と決めつけて悪く言い、集団で攻撃する行動は(彼らは正義感や被害者意識からで)、煽動の“土壌”にハマった振る舞いになりがちです。
気をつけましょう!飲み込まれないように!!
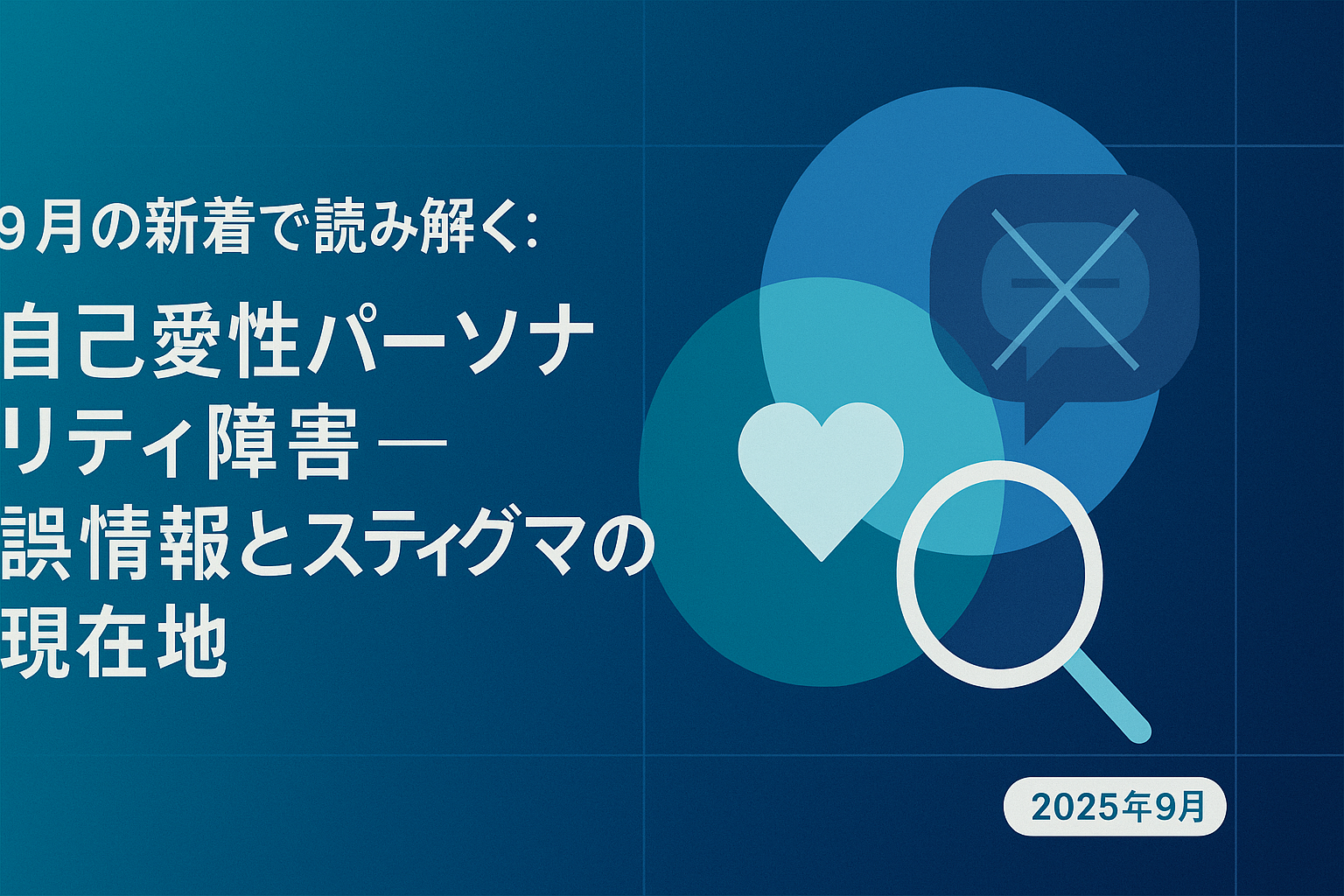
僕のようの前記した問題の本質が見えるようになってくると、彼ら(匿名アカウント群)がやっていること(発信内容)は興味深い現象であり、分析することで色々と学びになる部分もあるとわかります。
騙されていたって気づいた人は争わないように!
時間の無駄です。自分を大切にしてあげてください。

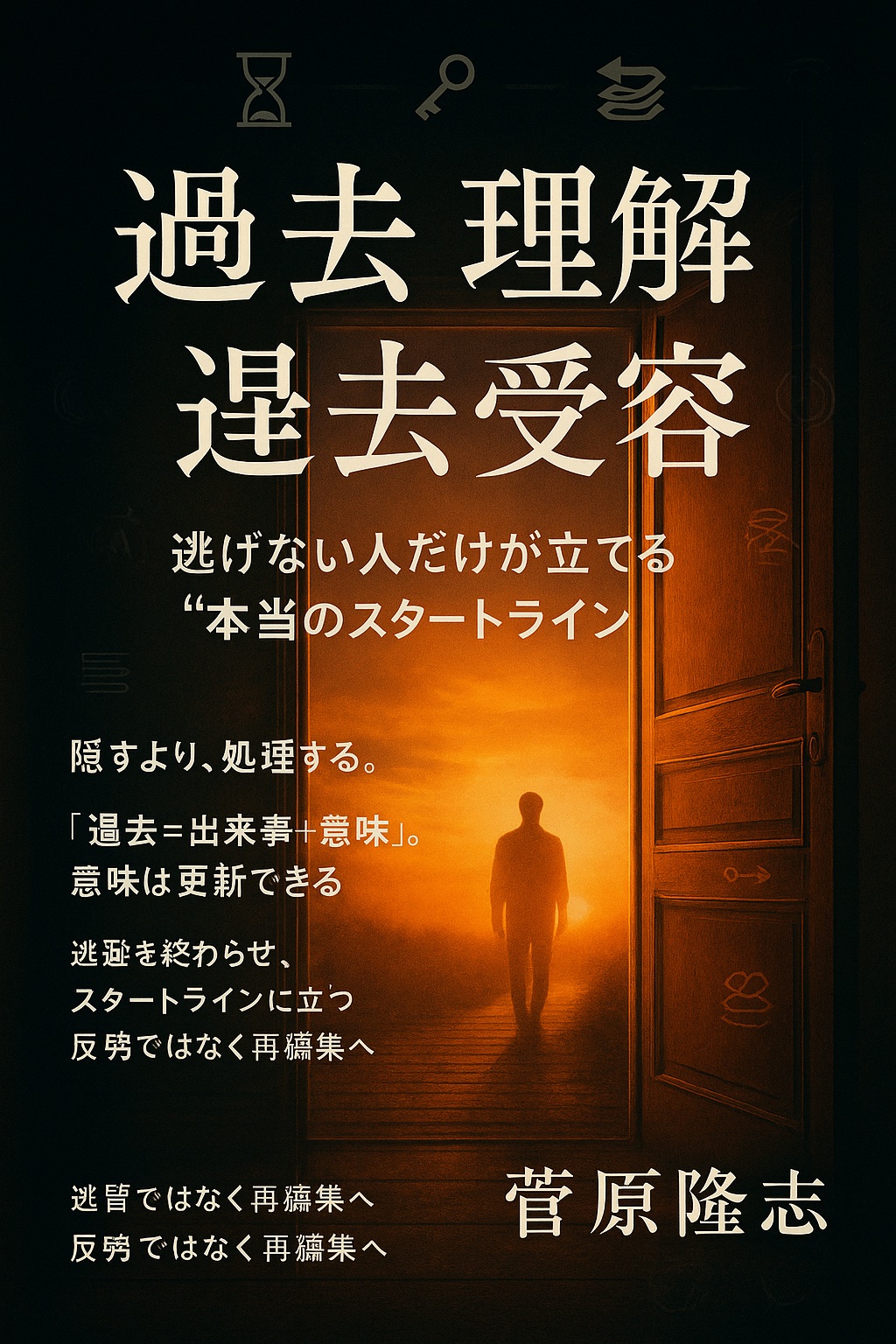
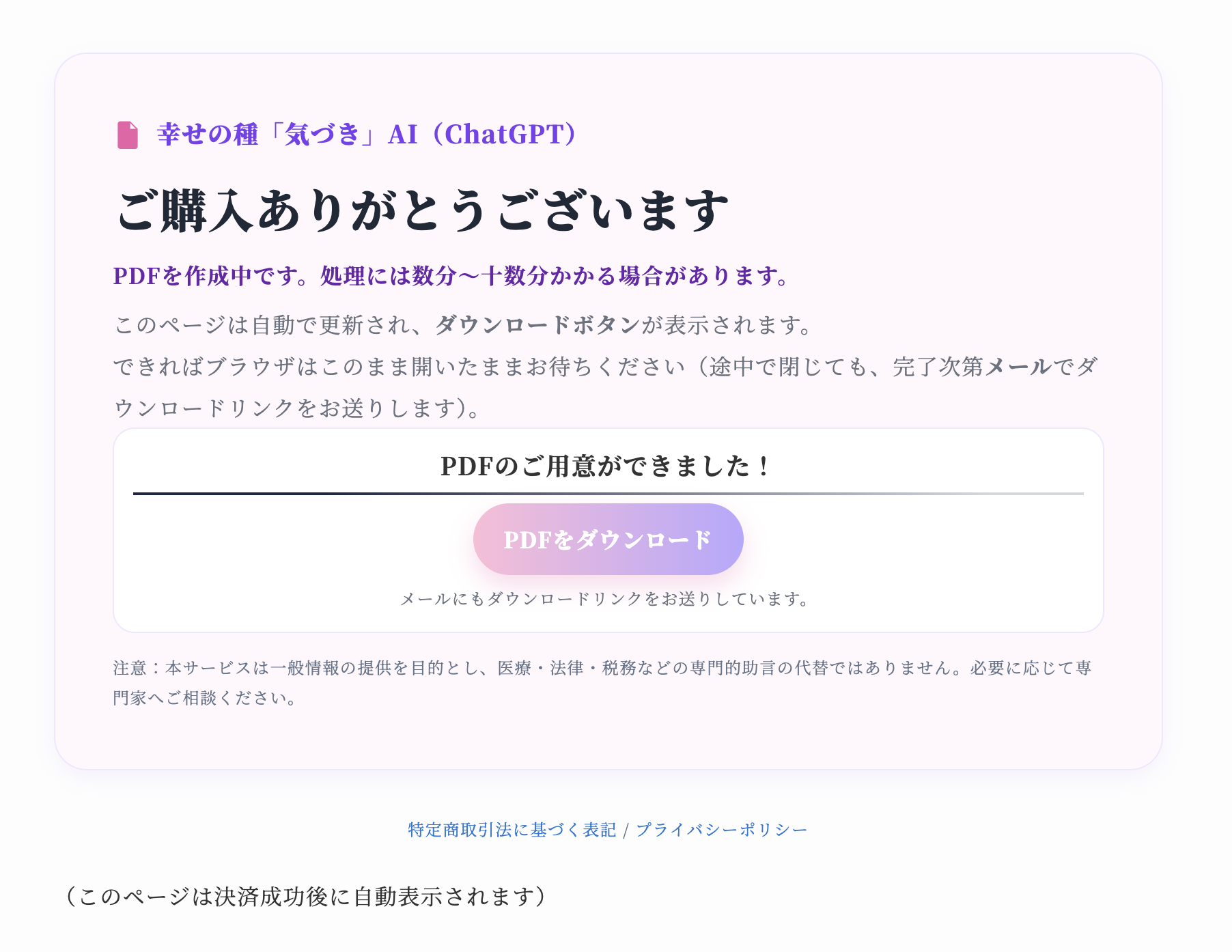
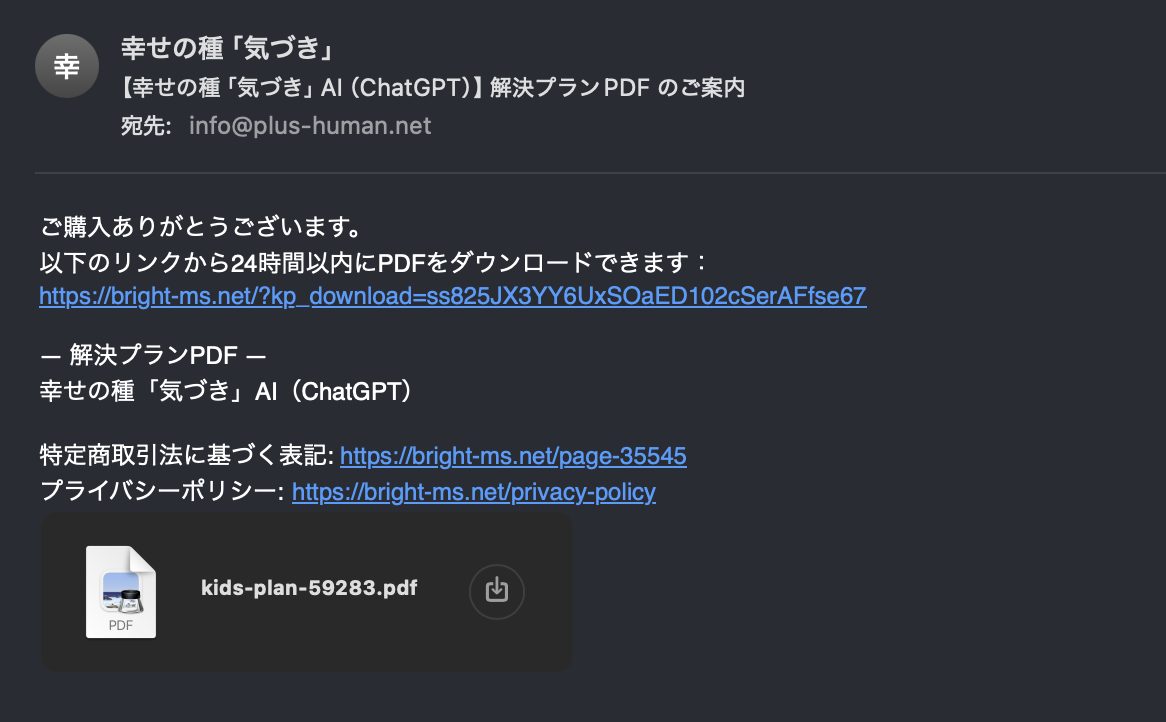
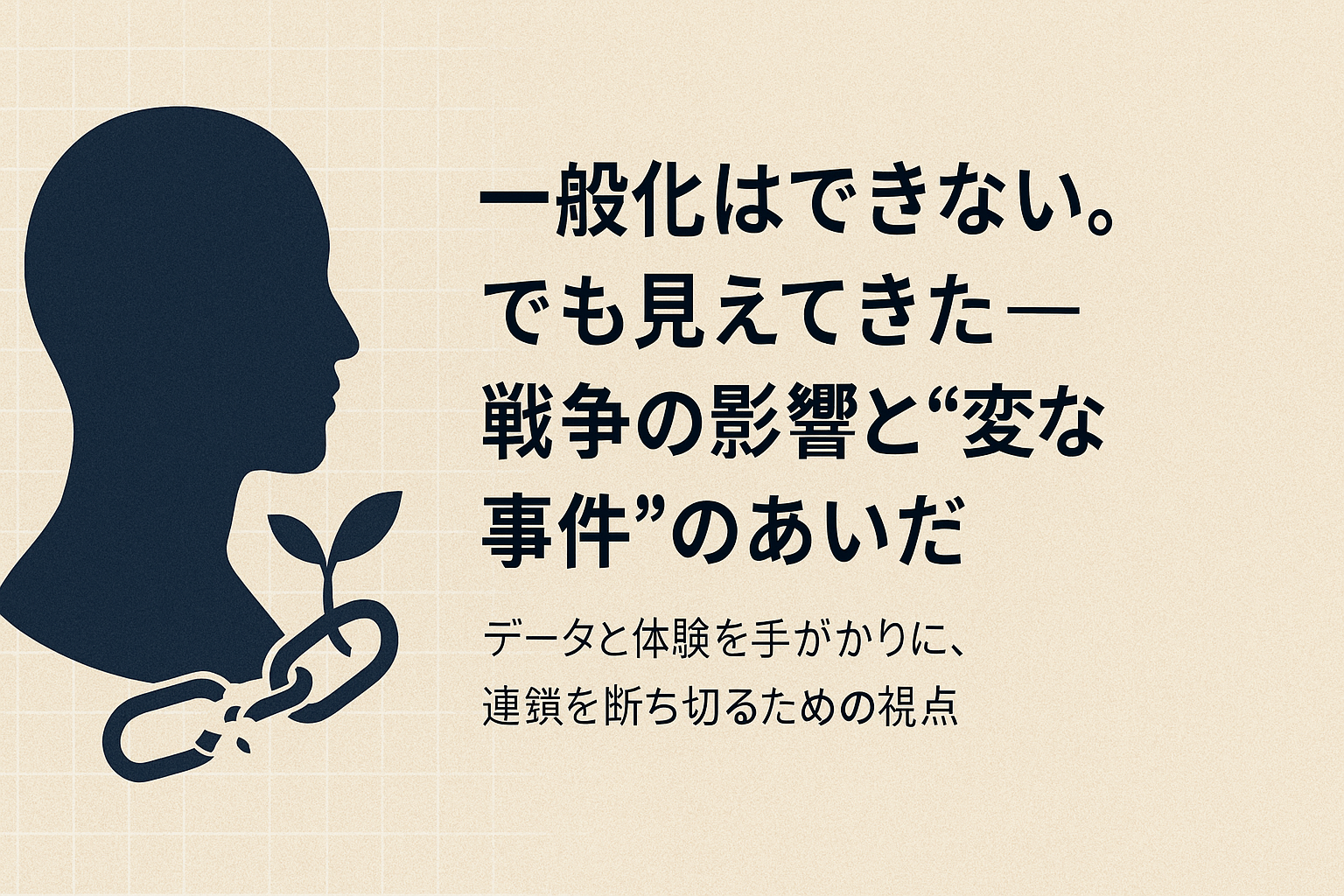


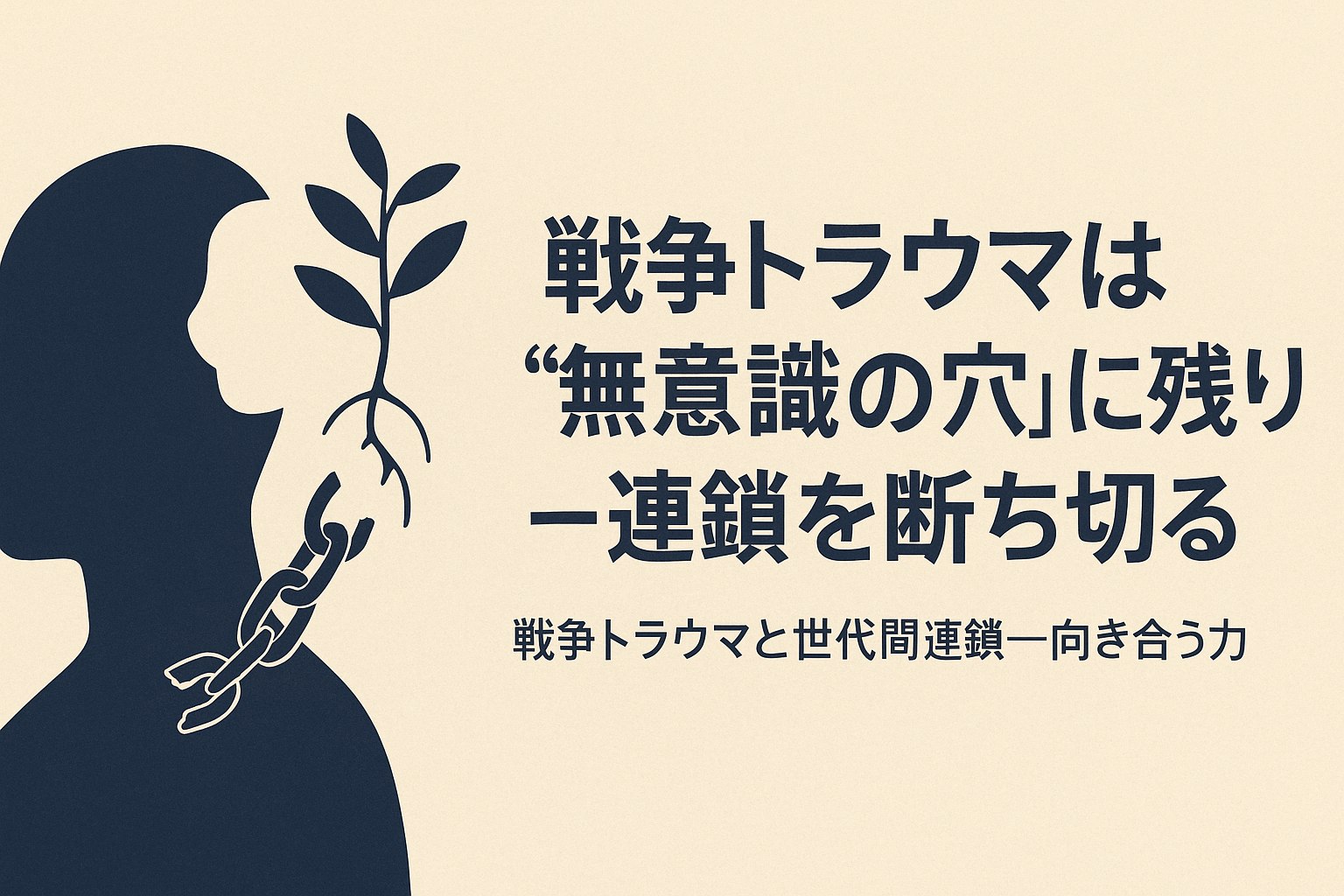



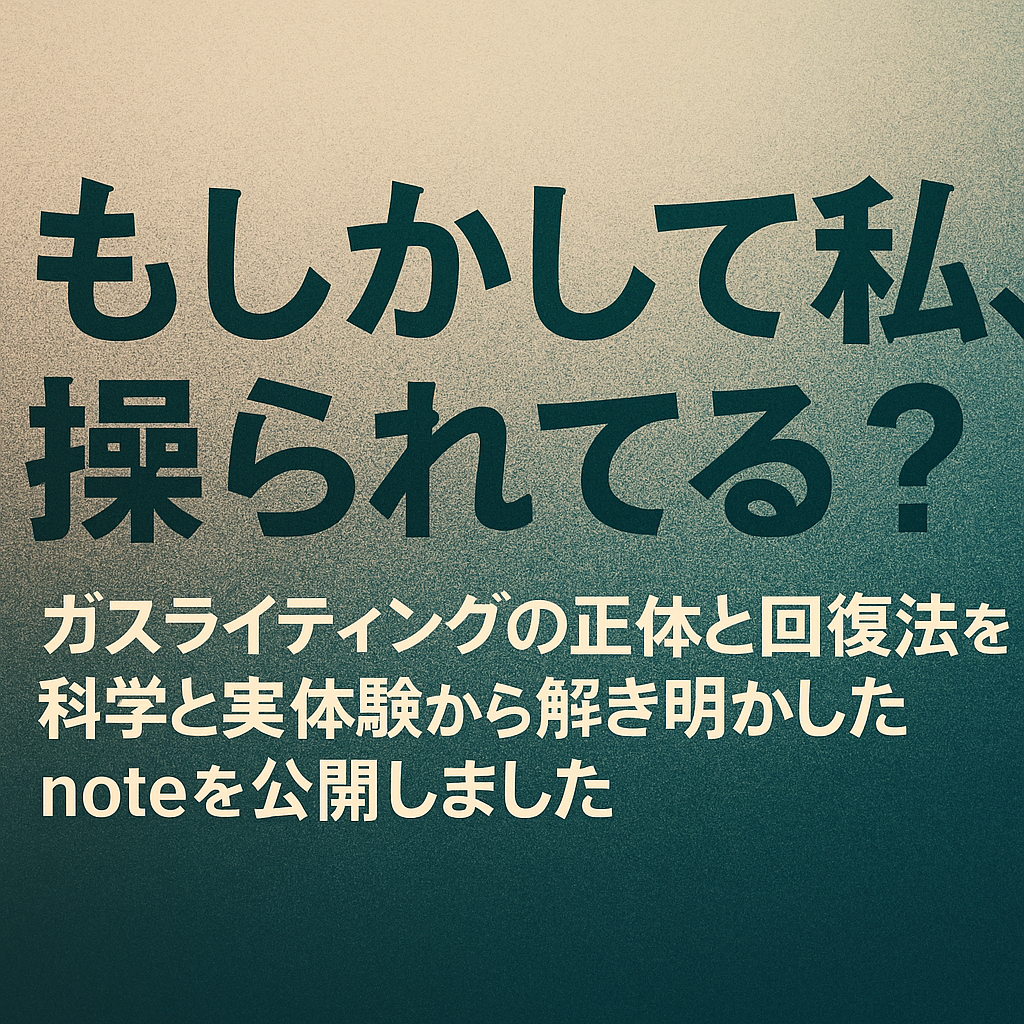

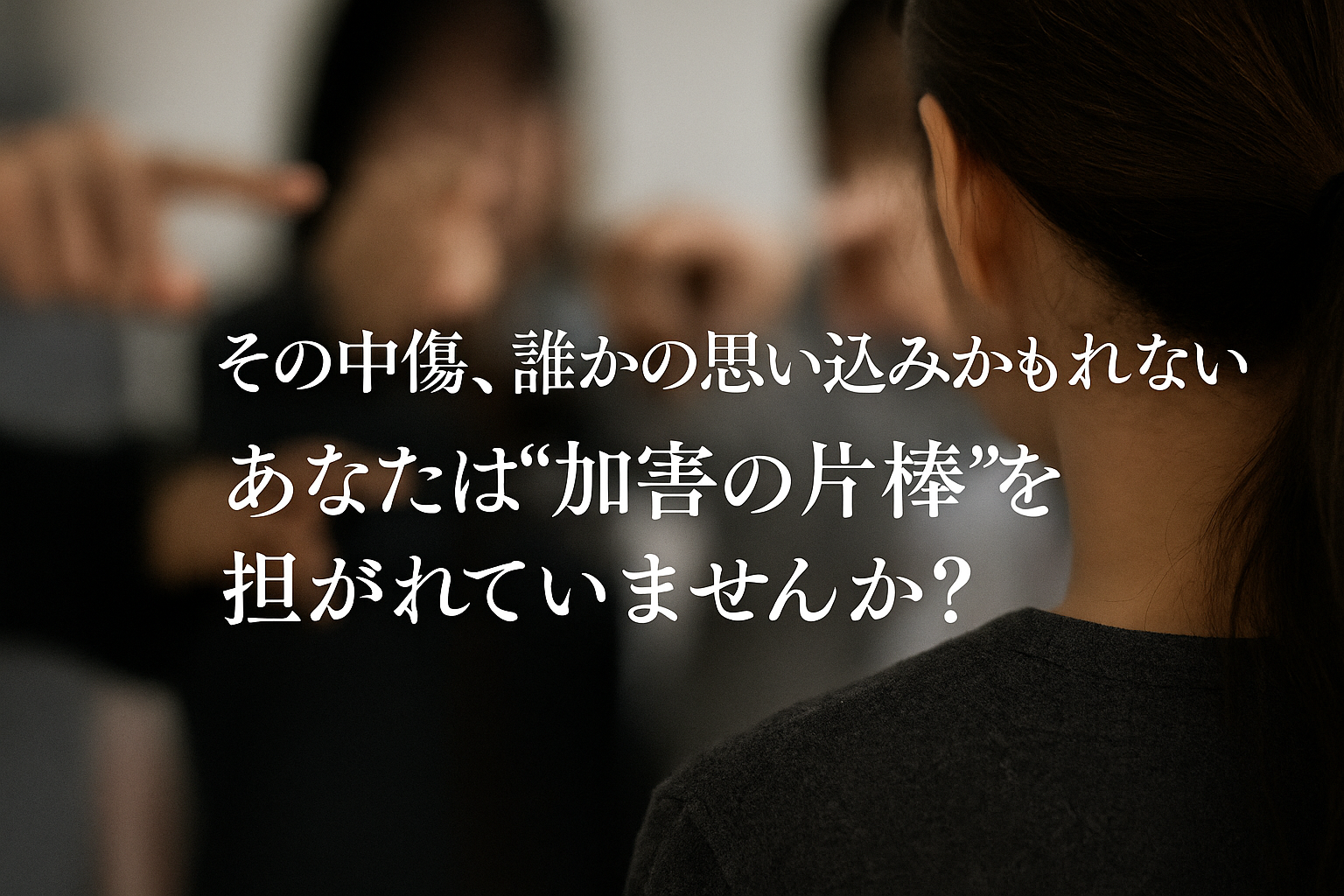
コメントを投稿する