 これはあくまでも個人的な意見であり、極一部のお話です。今から約14年くらい前に「おかしな空気」が作られていましたね。それに倣わない者は「空気の読めないアホ」という刷り込みで、多くの人が無意識で恐怖し、その集団に流れる空気に染まっていきました。その後、一気に精神薬を飲む人が私の周囲でも増えていました。得体の知れない恐怖が酷くなる者や、酒に必死に逃げる者、手が震える者、いろいろ変化したと同時に薬を飲みだすものが増え、悩んでいる者には口を揃えたかのように「病院行ったら?」が一気に増えたと感じています。必要以上に薬を飲ませたがっている…そう感じました。
これはあくまでも個人的な意見であり、極一部のお話です。今から約14年くらい前に「おかしな空気」が作られていましたね。それに倣わない者は「空気の読めないアホ」という刷り込みで、多くの人が無意識で恐怖し、その集団に流れる空気に染まっていきました。その後、一気に精神薬を飲む人が私の周囲でも増えていました。得体の知れない恐怖が酷くなる者や、酒に必死に逃げる者、手が震える者、いろいろ変化したと同時に薬を飲みだすものが増え、悩んでいる者には口を揃えたかのように「病院行ったら?」が一気に増えたと感じています。必要以上に薬を飲ませたがっている…そう感じました。
当時私は、少年院から出てきて少し経った後でしたが、知人が「おかしな空気」に染まっていたので、関わることが嫌になりました。他にもあちこちで、まるで信者かのように精神薬を飲む人が増え出し、あちこちで生活保護を受けるには、こんな嘘をついて診断してもらえばいいよという話があちこちであり、精神障害者年金目当てや、生活保護不正受給で病気偽っていたものもいました。生活保護のお金で日々スロットに行き子育ては適当、頻繁に酒飲んで精神薬をたくさん飲んで、たまに隠れて覚醒剤をやっていたりする者などもいました。
そして、その者たちが正しく、それに否定をするものなら徹底し圧力をかけられ悪者のレッテルを貼られて集団から攻撃されるのです。おかしな空気でした。
その者たちは「真剣な話などゴミクズの気持ち悪い奴の話」だという感じで、連携し「真剣な者を追いやっていた」のです。それにより、どんどん真剣な者が減っていき、真剣な話をすること自体に恐怖する者が一人増え、二人増え、と感染するかのように増えていき、多くの人が思考停止状態になりました。そして彼らは口をそろえて「お笑いみないの?おかしくない?」と同じような事を言ったり、同じような考えを持っていました。「お笑い番組」を見ない者を否定して嘲笑していくのです。まるで信者のように。
丁度、先日読んでいた本がこちらです。
こちらのP150から引用します。
権力者に従う事が「重要ですよ」と、くり返しくり返し刷り込むわけです。また、バラエティやお笑いでは、面白おかしく脚色したどうでもいいような話を、視聴者に「重要度が高いですよ」と刷り込みます。スタジオでちょっと真剣な話が行われると、そこにお笑いタレントの「世の中こうせなあかんとか、そんな難しいこと考える暇あんねんやったら、オレは目の前の焼酎が飲みたいねん!」というリアクションがかぶせられます。同時に、人々が爆笑する効果音が流され、「重要ですよ」と刷り込みます。すると、視聴者もそれに倣おうとします。
「イヤな気持ち」を消す技術
より引用
そう、こちらです。この刷り込みより私の周囲はおかしくなっていったと、私は考えています。この「真剣になる事や何故と追及することをおかしいとする空気」により、多くの人が倣っていったのでしょう。あるお笑い番組依存だった人は、かなりのモラハラ攻撃者だったのですが、自覚が出来てくるとこう言いました。「集団の空気が怖かったから、心理的に仲間になっていないと自分がターゲットにされるのが怖かった」と。
このように、いつでもどこでも、自分を見失いそうになる刷り込みは、どこにでもあるものです。大事なのは流されずに自分だけの自分の考えを持てるかどうかですね。
日々、流行や周囲の情報に流されて浮遊霊のようにふわふわしていると、自分が薄くなっていくのです。モラルハラスメント界とは実に巧妙です。
よくある質問 AI生成
この記事に関連するよくある質問をAIが自動生成しました
Q1. 「おかしな空気」や集団心理の影響から自分を守るにはどうすれば良いですか?
他者の意見や流行に流されず、自分の価値観や考えを持ち続けることが重要です。情報を多角的に分析し、批判的思考を養うことで、集団圧力に流されにくくなります。
Q2. 精神薬や生活保護の不正受給が社会に与える長期的な影響は何ですか?
不正受給が増えると、制度の信頼性が低下し、本当に必要な人への支援が妨げられます。また、社会全体のモラル低下や格差拡大につながる恐れがあります。
Q3. テレビやメディアによる刷り込みを防ぐ方法はありますか?
自分の情報源を多様化し、批判的な視点を持つことが重要です。また、メディアの意図や背景を考え、自分の意見をしっかり持つことで、影響を受けにくくなります。
Q4. どのようにして自分の考えを持ち続けることができるのでしょうか?
自分の価値観や信念を明確にし、日常的に振り返りや自己対話を行うことです。情報を受け取るだけでなく、意見交換や読書などで思考を深める習慣も効果的です。
Q5. このような社会的圧力や刷り込みに抗うために、個人ができる具体的な行動は何ですか?
自分の意見や考えをしっかり持ち、周囲の意見に流されずに行動することです。また、疑問を持ち続け、情報の真偽を見極める努力や、仲間と意見を共有し支え合うことも大切です。
- 1. https://www.amazon.co.jp/gp/product/4894515369/ref=as_li_qf_sp_asin_il?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4894515369&linkCode=as2&tag=angel048-22 https://www.amazon.co.jp/gp/product/4894515369/ref=as_li_qf_sp_asin_il?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4894515369&linkCode=as2&tag=angel048-22
- 2. 「イヤな気持ち」を消す技術 https://www.amazon.co.jp/gp/product/4894515369/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4894515369&linkCode=as2&tag=angel048-22


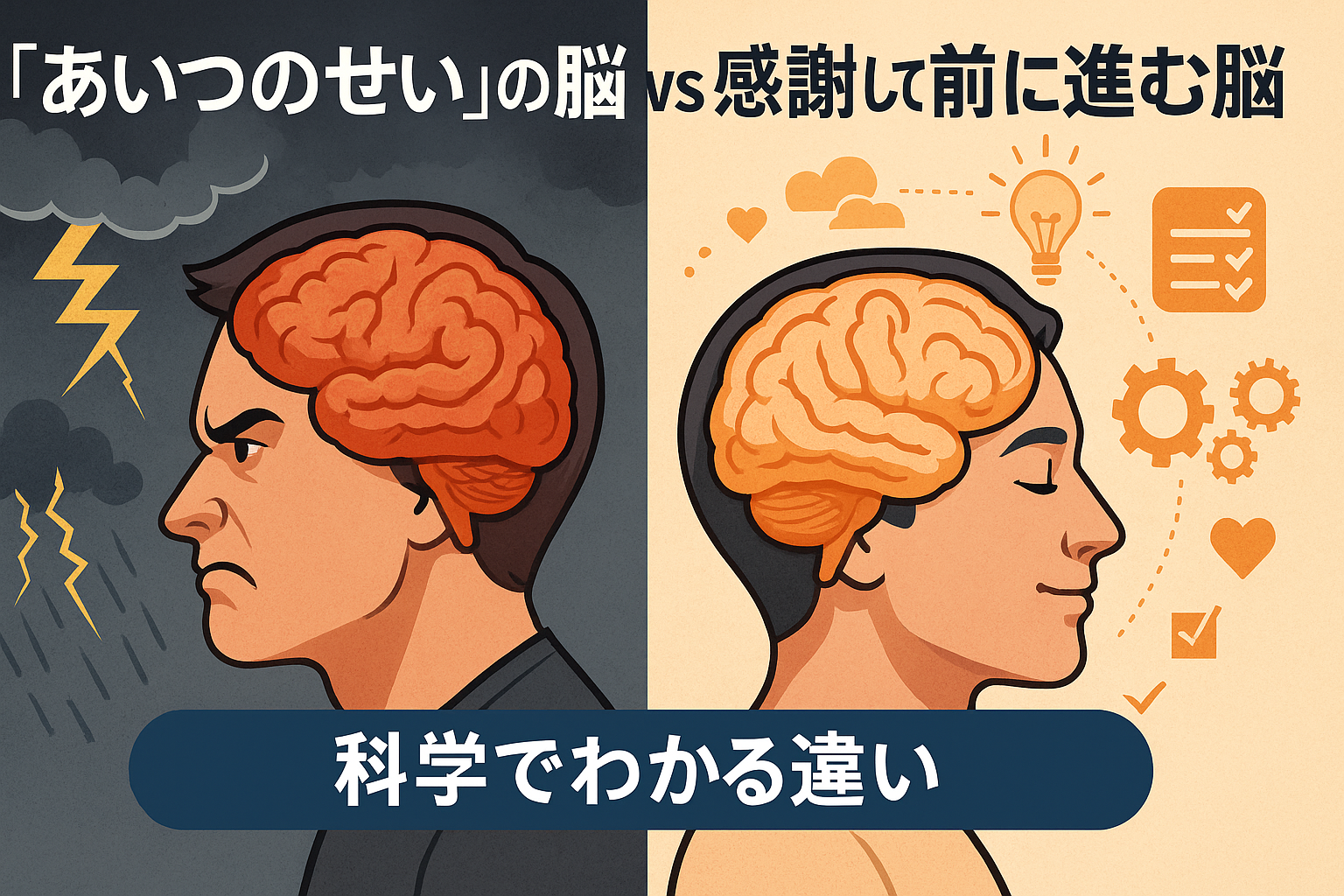



コメントを投稿する